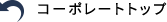自動車業界ライブラリ > コラム > 顧客接点でもっと仕事をしよう!
顧客接点でもっと仕事をしよう!
◆愛車コンピューター診断、マツダがメニュー化
<2007年11月20日付日刊自動車新聞掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【情報開示による「納得感の見える化」】
マツダは 2008年度中にも故障診断機を活用して車両電子制御システムの診断結果を顧客にリポートするサービス「愛車コンピュータ診断」を始める。
パワートレインからブレーキ、エアバッグ、エアコンなど 17 項目にわたる電子制御システムをチェックし、詳細な診断結果シートを出して顧客に説明する。つまり、人間ドックで行われる検査や問診のようにプロの目線でお客さんの目には見えないクルマの内側を診断した結果を顧客に分かり易い形で伝えるサービスだ。
同サービスは単独では有料で、定期点検などと組み合わせた場合には無料で提供する方針で、一部の販社では試験的にサービスを実施しており、顧客からは高い評価を得ているとのことである。
自動車整備にはブラックボックスがつきまとうものである。顧客が特に不具合を感じていないところまで整備・修理・交換した場合、顧客側は不安・不満を感じているのに現象が再現できないからという理由で放置された場合、いずれも顧客はプロのサービスとその対価に懐疑心を抱きがちである。
「愛車コンピューター診断」は、そうした顧客の懐疑心を払拭するために敢えてプロの手の内を明かすものであり、「納得感の見える化」を行なうものである。
「納得感の見える化」とは、かつて本誌で寺澤が指摘したアフターマーケット業界での成功のキーワード(下記 URL 参照)で、「標準化」(誰でもどこでも同じ成果を得られる)、「シグナリング」(不安・不満に対する保険・補償がある)、「情報開示」(不安や不満の源泉にある売り手・買い手間の情報の非対称性を取り払う)の 3 つの手法がある。
このうち昨今注目を浴びているのが、第三の類型である「情報開示」の重要性である。別に J-SOX や金融商品取引法などといった大きな問題をここで指摘するまでもない。
自動車市場でもかつてリコール隠しが問題になったが、中国製食品、不二家、赤福、石屋製菓、マクドナルドなどで起きた問題をめぐって、消費者はプロが開示している情報の信憑性や、プロが手の内に隠している情報の内容や整合性に対してとりわけ神経質になっており、情報を出し惜しんだり、情報を歪めたりする事業者は市場からの撤退を迫られる状況が起きているからである。
「愛車コンピュータ診断」は、こうした社会・市場の空気を先取りして、業界に先駆けて「情報開示」を行なうものだと評価できる。
【情報開示のリスクとのバランス】
情報開示によって顧客に対する「納得感の見える化」が可能だとしても、情報開示には諸刃の剣的なリスクを伴う。
実際、「愛車コンピューター診断」は故障診断の結果をリポートすることで自社の整備入庫を流出しかねない危険性をはらんでいる。
故障診断機はディーラーの競合である一般整備工場には普及しておらず(一般整備工場 72,904 の内 10 %弱の普及と見られている)、マツダディーラーが故障診断機を持っていること自体が競争力となっている。
その診断結果をリポートすることは、診断だけはマツダディーラーに依頼するが、そのレポートを相対的に工賃の安い一般整備工場に持ち込んで不具合箇所の整備・修理・交換は当該整備工場に依頼するという事態を招きかねないと考えられるからである。
このように情報開示という方法には本来公開して然るべき自身の恥部だけでなく、公開の必要性や合理性のない競争力の源泉までも曝け出しかねないリスクを伴う。従って、情報開示は「納得感の見える化」によって得られるものと、競争力の源泉の流出によって失うものとのバランスで検討されなければならない。
【ファンタジーを売る】
先日、弊社のメンバーの一人(「AYA の徒然草」の筆者)が自動車業界では伝説の営業ウーマンとして有名な林文子さん(現ダイエー副会長)の講演で聞いてきた話を社内でシェアした。
ホンダのトップセールスであった彼女は当時一日 100 件の自宅訪問を行なっていたという。さぞ苦痛だったのかと思えば、それまで別の会社でアシスタント的な仕事ばかりをやってきたため、会社を代表して一人で顧客に会い、「自分の名刺を渡すことが嬉しくて仕方がなかった」、「とにかく人と直接話をすることが大好きだった」、だから「仕事が大好きだった」のだそうだ。
BMW に移籍した後は来店商談が普通になったが、それでも来店客があると男性セールスが店内に立ちっぱなしでいる中、真っ先に飛び出して駐車作業は自分が請け負っていたらしい。
彼女が大事にしていたのは顧客接点である。
第一にどれだけ沢山のお客さんとどれだけ早く会うかという顧客接点の数とスピードを重視していたわけだが、同時に顧客接点の内容、質も大事にしていた。
ホンダのトップセールスだった当時の林さんは、「車は好きだったがメカニカルなことは分からないし、説明できないので、お客様には自分の経験を踏まえて情緒的な説明ばかりをしていた」そうである。「この車を手に入れると、お客様の生活はこんな風に変わりますよ」とか、「この車に乗ると、こんな楽しいことができますよ」といった内容である。
これに対して当時の男性セールスは、カタログを出してスペックの説明ばかりをし、顧客が理解できずにいると「乗ってもらえば分かります」と試乗ばかりを勧めていたという。
それにも拘らず、林さんのビジネスは紹介客で賑わう一方、男性セールスは「なんであんな車のことを何も分からない女がトップなんだ」と負け惜しみを言うばかりだったそうである。
この違いはどうだろうか。
男性営業マンは商品を売っていたのに対して、林さんはファンタジーを売っていたのである。また、男性営業マンが売っていたものは、顧客でも読めば、あるいは乗れば、分かるものか、読んでも乗っても分からないものかのどっちかだったということである。そして、そもそも顧客接点の数とスピードが違う。
そのように考えると、「愛車コンピュータ診断」の別の意味合いが見えてくる。
治安の悪化でオートロックマンションが普及して飛び込み訪問ができなくなり、個人情報保護法によって DM 配りも簡単ではなくなったいま、顧客接点の数とスピードを確保するメニューが求められている。
そのうえで顧客と何を話すか、顧客に何を伝えるか、顧客接点の中身、質が問われているわけである。「どこを直しておきました」という情報だけでは成り立たないのは当然のこととして、「どこに不具合がある」という情報ですら顧客接点に立つプロが話す中身としては不十分だとマツダは判断したのかもしれない。
「その不具合が生じた原因としてはこんなことが考えられる。だから、今後こういう保管の仕方に変えてみてはどうか」、「不具合とまではいえないが、今後こういう問題が生じてくる可能性があるから、今後はこういう運転の仕方にしてみてはどうか」、「今後こういうメンテナンスを行なえば、燃費がこんなによくなって一ヶ月の燃料代がこんなに下がるかもしれない」
レポートには書いていないし、症状には出ていないから、顧客には読んでも乗っても分からないようなことまで、プロだからこそ色んなアドバイスが受けられる。ディーラーのサービス工場は、人間ドックの診断結果を踏まえたドクターの話を聞くような場所であるべきだ、プロのメカニックとはそういうファンタジーを売る仕事をする人間のことだと再定義したものではないだろうか。
そのような場所、そのような仕事をする人たちから顧客が流出することはなく、集まってくるものだというのは林さんの事例が実証しているのではないかと思われる。
【顧客接点でもっと仕事をする】
顧客接点に立っているのは何もディーラーの営業マンやサービスマンだけではない。自動車メーカーに自社製品の採用をお願いしに行くサプライヤ、自動車メーカー社内でスタイリング案を披露するデザイナー、新しい情報システムの導入を勧める SIer、新たに開発した製造プロセスを展示会で紹介する設備メーカーのメカニック、全ての人が顧客接点に立っている。
それらの全ての人たちが顧客接点の数を増やすこと、スピードを上げることは心掛けているかもしれない。だが、比較的陥りやすい間違いが、カタログスペックの読み上げや、実験結果の詳細なデータの報告に留まってしまうことだ。
顧客は読めば分かることや、読んでも分からないことには関心がない。大事なことは、相手の話を聞けば自分にとってどんないいことが起きるのか、どのくらいすごいことなのか、それにはどうしたらいいのか、全て相手の視線に立って、相手が聞きたい話を相手が聞きたくなるように話すことである。
以前、ある自動車メーカーの事業開発部門に革新的技術を持つベンチャー企業を紹介する仕事をしていた。その際に彼らから決まって求められるキーワードが 3 つあった。正にこれが相手が求めるファンタジーであろう。
・ Value (その会社の製品を使うと当社にどんなメリットがあるのか)
・ Edge (それを使うと世界一になれるのか世界初になれるのか)
・ Expectation (そのために当社に期待するのは共同開発か投資か特許権の買取か)
筆者自身を含めて顧客接点に立つ全てのビジネスマンは顧客接点でもっと仕事をしよう。それは顧客接点の数を増やし、スピードを高めて、もっとファンタジーを売ることである。
「Drive Your Dreams」、「SHIFT_the future」。自動車メーカーが売っているのは、自動車という製品ではなく、夢や未来なのだから、我々自動車業界人が売るものも当然ファンタジーでなければならないのである。
<宝来(加藤) 啓>