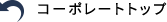自動車業界ライブラリ > コラム > 2004年度、企業買収価値、トヨタが首位
2004年度、企業買収価値、トヨタが首位
<2004年11月01日号掲載記事>
——————————————————————————–
企業の合併・買収(M&A)が活発になる中、日本経済新聞社が株式時価総額や財務諸表を使って 2004年度の「企業買収価値」を計算したところトヨタ自動車が 18 兆 4000 億円と首位になった。トヨタは 1年間の買収価値増加額でもトップである。
この企業買収価値というのは、ざっくり言ってしまえばその会社を買収するにはいくら必要なのかという金額である。今回のニュースによると日本の企業の中ではトヨタが最も高いとのことだが、最近中間決算において発表した純利益 5840 億円という突出した業績を見ても、これはある意味頷ける結果といえるだろう。
そしてこの企業買収価値(A)は「株式時価総額(B)+有利子負債(C)-金融資産(D)」で算出される。
この数式を誤解を恐れずに簡単に説明すると、ある企業の発行済み株式の全てをその時価総額である(B)円で買えたとしても(上場会社の株式を公開買付・TOB しようとした場合はプレミアムが発生することが多い為、現実的には時価総額=購入価格ではないであろう)当該企業には(C)円の借金があり、一方で(D)円の現金及び同等物をもっていて、結局差し引きすると(A)円必要ということである。
別の言い方をすれば、企業を 100 % 買収するには発行株式を全て取得するとともに、有利子負債を引き継ぐ必要があるが(全ての発行株式の総額が株式時価総額(株価×発行済み株式数)である)その買収される企業が現預金や運用目的の有価証券(両方あわせて金融資産と称す)を持っていれば、結果としてそれらを有することになる為、買収直後に売却すれば、実質その分の買収金額が減ることになる、ということである。
ともあれ、これで買収に必要な金額というものが算出されることとなる。
そしてこの企業買収価値を構成する要素の中でも根幹となる、特に重要な要素が株式時価総額である。これは概念的には貸借対照表の資本の部(株主資本)を株式市場が時価評価したものということができる。
株式市場に参画する投資家はアナリストの意見等を参考にしながら、その企業の現状の事業状態や財務諸表、更にはその企業の将来的な事業性といった要素を加味して株を売買し、その結果として株価は一定の数値に落ちつき、また日々変動していく。将来性といった曖昧な要素が株価という数字に変換されるわけである。
このような株式の時価が公表されるのは上場している企業に限り、上場していない企業の場合は公表されない。であるため、例えば今回のように企業買収価値を算出しようとしたら、不特定多数の投資家による市場売買の結果として収斂した株式の評価方式とは異なる方法で株式時価総額を算出しなければならない。
評価方法には様々なあるが、DCF (ディスカウントキャッシュフロー法)などは代表的なものの一つである。そのコンセプトを乱暴に言うと将来的にこの企業はこのくらいキャッシュを稼いでいきそうだから、現在の価値はこのくらいだろう、ということで株式時価総額が決定されるというものである。計算式等の詳細は本メールマガジン vol.37 の「今更聞けない財務用語シリーズ」にて紹介されているのでここでは割愛する。
さて、これまでの話を踏まえると上場している企業の場合は株式市場により評価されるということになるが、評価される企業の側からすると株式市場は自分達の企業の価値を正しく把握、認識できているのかという懸念もあるだろう。
今回のニュースに照らしていうと価値が正しく把握されず株式時価総額が低く評価されてしまうと結果として企業買収価値にもマイナスの影響を与え、買収されやすいと判断されることにもなりかねない。
そういった事態を防止するためには株式市場に対して自分達の企業の価値を正しく伝える IR (Investers Relations)という行為が非常に重要なものとなってくるのである。
しかし、一方でまた、例えば企業内の研究開発部門に所属する社員などは IR等の管理部門の社員が自分達の研究開発の価値を正しく把握、認識し株式市場へ伝達しているだろうかという懸念を持っているかもしれない。
多くの企業で研究開発部門のプロジェクトに対して投資収益率などの指標を用いた管理を導入しているケースが見受けられる。
投資収益率などの指標による研究開発プロジェクトの管理などは、当該技術の専門家ではない管理部門の人間がその価値を把握しようとする行為であるが、株式市場における参画プレーヤーも技術の専門家でないことが多いため、個々の技術者からすれば直近のリターン以外の形の価値を主張したい場合もあるだろうが、最終的には数値への変換を伴う価値伝達は避けられない。
ここで重要なのは企業が様々なステークホルダーと接点をもちつつ企業活動を営んでいく以上、自身のやっていることの価値を相手に伝えなければならないということなのである。
それは、「価値を伝える」相手として最も大切なステークホルダーである「顧客」は勿論のこと、その一番重要な価値伝達を支えるための、リソースの提供者である「株主」に対しても同様に必要なことなのである。
<秋山 喬>