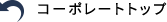自動車業界ライブラリ > コラム > インテグラルとモジュラーの共生を考える
インテグラルとモジュラーの共生を考える
◆ソニー、超薄型TV商品化
<2007年4月12日日本経済新聞朝刊掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【オープン・モジュラー世界との出会い】
東京ビッグサイトで開催された最新の画像ディスプレイ展示会「第 3 回 Display2007」に出かけてきた。
話題のソニー 27 インチ有機 EL テレビの画像はコントラスト比 100 万:1というだけあってその画像は正に鮮烈であったし、同社からカーブアウトしたエフ・イー・テクノロジーが展示した電界放出型ディスプレイ(FED)も CRT をベースにしたシンプルな作りだというのにその動画表示の精緻さに驚いた。同社の製品は主に放送局などプロフェッショナルユースを意識していると言うが、双葉電子工業は FED の省電力性や視認性の高さに着目して車載を主用途の一つと想定しているらしく、インパネやコンビメータ内に置く小型ディスプレイを数々展示していた。
全体としては車載用の展示が少なかったことは残念だったが、薄型といえば家庭用 TV、LCD (液晶)、FPD (フラットパネル)というのが定番だった世界から、対象市場・用途、発光・表示アプローチ、形状・大きさの面での進化や多様化を感じさせる有意義な展示会であったと思う。
だが、それにも拘らず会場全体の視察を終えた後、何か納得の行かない複雑な思い、少し暗澹たる気持ちになった。電子業界の皆様には申し訳ないが、「日本のものづくりは本当にこれでいいのか」という問題意識に取り憑かれ、執筆している今この時点でもその答を見付けきれずにいる。それは会場全体を見渡した時点で直感し、実際に歩き回ってみて確信に至った思いである。
まず、メイン会場(厳密には「第 3 回 Display2007」と題した独立の展示会)には前述のような最新の技術開発成果(の一部もしくはダウングレード・バージョン)が展示されている。出展者の数は少なく、1 社あたり広いスペースを使っているので、華やかで堂々とした印象である。その派手な展示の傍らに開発に携わったと思われる技術者たちが説明に立っている。説明そのものはあまり上手とは言えないが、開発者としての高い志や熱い思い、自分自身やチームの知識・経験・技術に対する愛着や信頼、時間・コスト・品質などの制約条件のもとで目標を達成するための禁欲的なプロセスがひしひしと伝わってくる。
思わず頭を下げたくなる空間である。
その直ぐ横は厳密には別の(「第 2 回 FPD 部品・材料 EXPO」と題した)展示会で、要はメイン会場で見た最新ディスプレイ製品を構成する部材の展示コーナーである。メイン会場とはうって変わって多くのサプライヤが小さなブースにぎっしり出展し、最新製品の内側に詰め込まれた技術要素はそこで漏れなく機能的・構造的に分解・整理されて公開されているという印象である。
会場を更に奥に進むと、また別(「第 17 回 FINETECH JAPAN」という名前)の設備装置の展示コーナーとなる。メイン会場の 4 倍以上のスペースにメイン会場出展者の 30 倍程度の出展者が部材コーナーと同じ密度で入っている。メイン会場側に「検査・リペア・測定ゾーン」があり、通路を挟んだ向かい側が「製造装置ゾーン」である。最新ディスプレイの量産開発ラボ(実験・測定・解析)で必要とされるもの、量産工場で求められるもの一切合財が展示され、多様な選択肢すら用意されているという感想を持った。
【オープン・モジュラー世界の脅威】
筆者の感じたやりきれない思いとは、極論の謗りを恐れずに言えば、もし来場者がメイン会場で見た製品コンセプトに事業性を感じたならば、部材コーナーで必要なパーツを購入し、設備装置コーナーでラボ・工場設備を購入してきたら、今日からでも最新製品のメーカーになることができる、必要なものは設備投資に必要な経営者のリーダーシップと資金力だけ、という製品アーキテクチャやものづくり体系に対する驚きと不安・恐れである。実際に来場者の相当数がアジア訛りの強い英語を話す人々であった。
このように例えれば、筆者の驚きをご理解いただけるのではないか。東京モーターショウのメイン会場に展示された最新のハイブリッド車が隣のコーナーで、まるでベンチマーク用の競合車のティアダウンのように、それを構成する部品に完全に丸裸に分解されて販売されており、更にその隣のコーナーでそれを組み立てるためのライン一式が販売されていて、そこに海外企業の経営者たちが群がっている光景である。メイン会場はただのショーケースの位置付けであり、ビジネスはそれ以外のコーナーにあるとすら感じられたのである。
不安や恐れの種はどこにあるかと言えば、開発の先駆者たちの企画・構想やその実現のための知見、努力、時間、投資は、そのリターンを享受する前に一瞬にしてフォロワーにより模倣・再現され、報いられることがないばかりか、しっぺ返しを食らう恐れがあると思われる点にある。
日本の経営者は優秀な営業マン・技術者が上り詰めた形であって帝王学の知識・経験が少ないサラリーマンだから、経営の意思決定のスピードや徹底という面では不利な立場にある。加えて、資金力という面では総合メーカーが多く、特定の事業に資金を集中しにくい上に、開発工程で長期間・多大な支出を強いられる構造の日本企業はやはり不利である。
設備さえあれば誰でもキャッチアップできる製品であれば、価格勝負、コスト競争力の勝負になるが、そこが設備投資の規模が大きければ大きいほどコスト競争力が高まる産業だとしたら(電子業界は往々にしてそうである)、設備投資段階で勝負が決する極めてリスクの高い戦いとなる。リスクが高いから設備投資を見送り、製造は海外に委託しようという判断に陥りやすい。そうなると海外企業がすぐにでも生産受託できるように、製品やインターフェースの構造をできるだけシンプルに設計して、業界標準的なものになるようにオープンにしていくという発想になる。
その結果、結局、このような展示会形式や産業構造になって、また設備投資段階で決まる価格競争に陥るという悪循環が生じているのだろうと思われる。
これが、「オープン・モジュラー」の世界なのか、と改めてその恐ろしさを痛感するとともに自動車はそれと無縁でいられるのか、いられないとしたらどのように付き合っていくべきか、という点を深く考えさせられた。
【オープン・モジュラー世界を遠ざけていたもの】
東京モーターショウの例で見たとおり、自動車の世界で同じような光景に出会うことはなかなかない。それは、自動車の製品アーキテクチャがモジュラー(組み合わせ)型とは対極のインテグラル(刷り合せ)型の代表選手であったことに起因すると考えられる。
インテグラル型とは、特定の機能・性能を特定の部品・構造物に全面的かつ排他的に担わせるようなコンポーネントの括り(モジュール)を作ることが困難で、括られたコンポーネント同士をお互いに干渉や副作用なく自由につなぎ合わせること(インターフェース)も難しい類の製品の設計思想やものづくりの体系を言う。
例えば、ハンドリング性能は、サスペンション、ブレーキ、ステアリング、タイヤ、ボディ重量とその配分、駆動レイアウトなど複数の部品やプロセスから構成され、逆にボディはデザイン性、衝突安全性、軽量性、操縦安定性など複数の機能を担う。PC の処理スピードを上げるためにはクロック周波数の高いCPU を取り付ければよいといったような、機能と構造の単純結合が成り立たないのである。
また、万一機能と構造の単純結合に成功し、特定の部品に特定の機能の全てを独占的に落とし込んだとしても、インターフェース設計が各社ごと、車種ごと、場合によっては同一車種内でもバラバラなので、部品を集めてきても繋ぎ合わせて完成品にすることはできないし、無理に繋ぎ合わせたとしても市販レベルの性能・品質は発揮できない(自動車メーカー自身が完全な技術指導や部品供給の下に CKD キットのような形でライセンス生産を許諾するケースを除いて)。
だが、自動車がインテグラル型であり続けて来られたのは、次の二つの基礎条件が備わっていたからだと考える。
第一に、自動車の未公開会社性である。
自動車は人生で二番目に高い高価な商品であること、素人が操る機械の中で唯一人の殺傷能力を持っているところに究極の商品特性がある。だから、ゼロデフェクト、源流問題解決による完全性の追求が製品要件になる。
家電製品や PC であれば、少々不具合があっても部品交換対応で顧客が納得しがちである。精々数万円~十数万円の初期投資であり、生死に係る事故になることも少ないからである。
また、メーカーの側でもゼロデフェクトレベルの品質管理に掛けるコストよ
りも、クレームの都度、部品交換に応じた方が安上がりである。だから、保証の範囲内であればルーティーンとして、メーカーの顧客相談窓口やサービス部門だけで問題が処理され、保証が切れていた場合は家電量販店が延長保証の範囲内で自己解決したり、メーカーの補修部品部門とのやり取りで解決してしまう。設計部門まで遡った源流問題解決が行なわれにくい構造になる。
これに対して、場合によっては年収の何倍にもあたる自動車に不良や不具合が見つかると顧客の信頼を失う上に、人の命に関わる事故の引き金にもなりうる。部品自体も高価な上に、事故の賠償やブランド資産喪失の損失まで考慮すると部品交換型の対応は経済的に見合わない。
だから、不良率を PPM 管理するどころか、ゼロデフェクトを自社にもサプライヤにも求める。その段階に到達するまでは商品を市場に投入しないし、万一市場投入後に問題が起きたら都度設計部門に報告され、真因分析を行って、随時設計変更が検討される。完全性要件がより厳しいのである。
完全性要件の違いが自動車をオープン・モジュラーの世界から遠ざけることとどう関係しているかといえば、「自社の業務スコープは開発まで、製造は第三者に委託」という役割・責任分担は成り立ちにくく、自社製造を前提に自社が品質保証できる形でモノを設計することが基本になる点にある。自社製造する以上は、誰にでも作れる形に製品やインターフェースを設計する必然性はないから、インテグラル的になる。
丁度、上場会社と違って未公開会社の場合は監査やディスクロージャ(情報公開)をさほど意識する必要はなく、寧ろ税務上の理由や銀行との関係性に応じて独自の財務諸表や管理体系を作りがちなことと似ている。
第二に、自動車の海洋国家性である。
世の多くの工業製品は他の社会ネットワークから孤立した据え置き型の存在では存続が難しくなり、外界との接続によってモビリティと空間統合性を持たせることが重要になっている。
プリンタやコピー機は会社でも家庭でも LAN との接続性が求められるし、デジカメもゲーム機も TV もオーディオもメディアカードやインターネットを通じた外部ネットワークとの接続性や外部空間との統合性が求められる。携帯電話やカード型乗車券には電子決済機能が不可欠の装備になった。
外界との接続性や統合性が商品力を決する製品要件となれば外部ネットワークと共通の言語でのインターフェースを持つ必要がある。インターフェースが自社固有のものであっては接続性に限界があり、商品力の成約になるから、極力シンプルで業界標準的なインターフェースの採用が求められるのである。外界とのインターフェースの結果として、製品相互の干渉や副作用が出てはまずいから、自己完結型の機能・構造設計にすることが求められることにもなる。
これに対して、自動車はそれ自体がモビリティを持っている。外部ネットワークとのコンタクトが必要なときには自ら動いていけばよい。また、住居と同様、そこが一つの完成された居住空間を構成しているから、その内部では空間統合性が要求されるものの、外部空間との統合性は求められない。
つまり、他の工業製品や自動車、社会インフラとの接続性や統合性はある意味でどうでもよく、従って(ワイパー、バッテリー、タイヤなど一部を除いて)インターフェースの単純化や標準化が進まず、オープン・モジュラー化の動機付けがなかったのである。
欧州など大陸性国家が隣国とのトラブルに常に悩まされ、苦労して統一・共通の価値基準や法体系を整備していったのと対照的に、日本や英国のような島国は固有性を保ったまま自分の欲するときには欲するだけ海を渡って行ったのと似たものがある。
【オープン・モジュラー世界の進出】
このような背景から自動車は概ねオープン・モジュラーの世界と無縁であり続けてきたが、現実には次のように基礎条件に変化が訪れつつある。無縁のままではいられなくなってきているのである。
第一に、自動車メーカー自身が自らの事情でモジュラー化を進めている。
1.市場が求める多様性と企業が必要とする効率性を両立するために、アッパーボディは差別化・専用設計としながら、プラットフォームやパワートレイン、構成部品、生産工程は共通化しようという考え方が主流になってきた(社内 完結のクローズド・モジュラー)
2.業界再編・統合が進んで企業を跨った形(ただし、主には資本系列内)での共同開発や成果の共有が進んできた(資本系列内でのセミ・クローズド・モジュラー)
3.安全性や環境性の要件に対応するために緻密な機能制御や新たなパワーシステムが必要になり、結果としてモジュラー型の電子・電気製品が多数入り込んできた(企業・資本を部分的に超えたインバウンド型セミ・オープン・モジュラー)
4.自動車メーカーの負荷が限界に達し、自らの権限・責任の一部を外部(主には系列の Tier1 サプライヤ)に移転せざるを得なくなってきた(アウトバウンド型セミ・オープン・モジュラー)
第二に、製品の完全性要件に変化の兆しがあること。
人の命を預かるという意味での完全性要件には変化はないものの、人生で 2番目に高い高価な買い物としての完全性要件には変化が生じつつある。
日本国内においても軽自動車が登録車需要を食い、登録車の中でも B セグメントが主流になってきている。自動車以外のところに消費者の関心や財布が向きつつあり、燃料の高騰や資源節約・環境保全の理由から、完全性と裏返しの高いコストを自動車に投じることを必ずしも望まない消費者が増えているのである。
これに加えて世界的に見ると今後の自動車市場の成長は低所得国に依存することが明らかで、各社とも 1 万ドル以下の商品開発を急いでいる。50 万円の製品に完全性を要求することは難しいであろう。
第三に、外部との接続性や統合性は自動車においても重要になってきている。
携帯電話や iPod のように自動車以上にモビリティの高い製品が普及し、自動車側がそれらとの接続性や統合性を要求され始めてきた。また、古くは VICS 情報の取得、ここ数年では ETC の普及、最近では G-Book mX のようなテレマティクスの進化、今後数年では路車間・車車間通信による ASV (先進安全自動車)実現のための ITS インフラ協調システムの導入などが背景にある。
このように自動車にも(フル・オープンとまでは行かなくとも)モジュラー型の製品やコンセプトが徐々にしかし確実に浸透してきているのである。
【オープン・モジュラー世界との共生】
これまでオープン・モジュラーの世界の恐ろしさばかりを述べてきたが、実際にはオープン・モジュラーの世界にも利点、見習うべき点はある。
第一に、開発に係る投資や工数(従ってコストやリードタイム)を節減できることである。
実際、ソニーが現段階で量産可能な有機 EL テレビは 11 インチのみで、話題の 27 インチはまだコストや生産性の面で量産計画が立っていないそうである。にも拘らず、というよりも、だからこそこの段階で製品開発の方向性を明確に示し、それに賛同・支援してくれる部材・設備メーカーを探すために敢えて公開に踏み切ったのだという。自動車にも部分的に応用可能な考え方だと思われる。
第二に、前述の結果として迅速かつ柔軟に商品の多様化やアップデートが可能になることである。新車効果が長持ちしなくなって久しいが、順列組み合わせ的に少変更や特別仕様車の投入が可能になれば都度市場に刺激を与えることができる。また、設計変更が必要になった際にも車両システム全体に影響を与えずに機動的にバージョンアップできるようになる。
第三に、クレームやリコールに対するリスク・責任負担が明確になることである。その結果、対応スピードが向上して顧客満足が改善し、原因調査や対策に係る負荷やコストを低減できる。
第四に、究極の後工程引き取り方式の実現に近づくことである。トヨタ生産方式は、顧客の注文を代表する販売計画に応じて「必要なときに、必要なものを、必要なだけ」供給し、在庫や作りすぎ等の7つのムダを省くものだが、バリューチェーンを突き詰めると PC の世界でデルが実現しているような BTO (Build To Order=受注生産)になる。
自動車メーカーの多くは現在CRP(Continuous Replenishment Program=連続自動補充方式)の進化形といわれるCPFR(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment=協同計画予測補充)方式によって、末端の受注・納車・在庫状況や過去の販売履歴を見ながら販売計画を立て、部品のオーダー・リードタイムや生産平準化、短期の予算達成など作り手側の要件も織り込んだ仕様や数量での見込み生産を行なっている。顧客の求める仕様や数量を代表してはいるものの、顧客の求める仕様や数量そのものではない。
BTO のような完全なプル型ではなく、プッシュ型の要素を多分に持っているわけだが、その背景には作り手側の柔軟性や迅速性にまだ課題を残しているためだが、オープン・モジュラーはその課題解決にかなり寄与するはずである。
では、そのような利点と脅威を持つモジュラー型ものづくりとどのように付き合っていくべきかであるが、要は完全なオープン・モジュラーが問題なのであって、部分的なオープン・モジュラーの考え方は共生可能であり、寧ろ上手く利用・活用していくべきであろう。
部分的なオープン・モジュラーには 4 つの類型があると思われる。
1.オープンの範囲(共同開発グループ)を限定する。
2.車両システムの一部だけをオープン・モジュラー型の設計とする。
3.製品設計はインテグラル型とするが、インターフェース設計はオープン・モジュラー型とする
4.逆に製品設計はオープン・モジュラーとするが、インターフェース設計はインテグラル型とする。
【オープン・モジュラー世界の進出】のところで述べたような自動車メーカー自身が進める社内完結型または資本系列内でのクローズド・モジュラーは上記の 1.または 2.に該当する。
インバウンド型セミ・オープン・モジュラーの場合、電子製品の開発には合弁会社を作って実質的には自社グループに取り込んでいること(パナソニックEV エナジーなど)、アウトバウンド型セミ・オープン・モジュラーの場合も、権限委譲先が主要な系列サプライヤであること(トヨタはアドヴィクスへの出資比率を引き下げ、ブレーキシステムの開発は同社に任せる方針を示したが同時に同社をグループの中核であるアイシン精機の子会社とした)を見ると、やはり上記 1.の形態だと考えられる。
従って、上記 1.や 2.の形態での部分的なオープン・モジュラー化は実現可能であり、既に実績があるわけだから、この方式の一層の追求がオープン・モジュラー世界との共生の一つのあり方であろう。
上記 3.の類型にはアイシン・エイ・アブリュの AT、上記 4.の類型にはアスモのモータに実例を見ることができると考える。
前者は現在オープン・モジュラー型ものづくりの代表国である中国で引っ張りだこの商品となっている。ハイブリッド・システムも一部外販されているのでこの形態に近いし、いすゞのエンジンもそうであろう。
後者はクルマのありとあらゆる場所・用途で使われるのでインターフェースは個別設計となるが、中身の構造や基本機能は大体標準化・共通化されており、組み合わせ型のカスタマイズが可能なようである。
つまり、上記 3.や 4.の形態(つまり製品とインターフェースを逆の製品アーキテクチャとする方式)での部分的なオープン・モジュラー化も可能であることが実証されているわけだが、それに加えて面白い調査分析結果が報告されているので、オープン・モジュラー型世界との共生の重要なあり方として検討の価値があると思われる。
東京大学ものづくり経営研究センター長の藤本隆弘教授は、「自動車部品産業における取引パターンの発展と変容」の中で、自動車部品を「内的相互依存性」、「外的相互依存性」という軸で分類し、そのマトリクスを用いてどのような製品アーキテクチャとビジネスモデルの営業利益率が最も高い傾向にあるかを分析している。
「内的相互依存性」とは製品設計がインテグラル型であることを意味し、「外的相互依存性」とはインターフェース設計がモジュラー型であることを示すものと思われる。
結論としては、製品設計とインターフェース設計を真逆にした場合、つまり上記 3.または 4. の形(モジュラー X インテグラル型)での部分的オープン・モジュラーの営業利益率が最も高いとのことである。
原因として同教授が上げているのは、「顧客の細かな要求に合わせてすり合わせを行なうタイプの部品の場合、(中略)都度自社製品の設計をすり合せていると、(中略)生産規模が限定されて儲からなくなるが、自社製品の設計を組み合わせで行なうことができれば、(中略)量産効果が生じて儲かりやすくなる」、「顧客の要求に合わせてすり合わせを行なわなくてもよいタイプの場合、自社製品の設計がモジュラー的だと、自動車メーカーから見てコスト構造が丸見えになるためあまり儲からなくなるが、自社製品の設計がインテグラル的だと、(中略)ブラックボックス的な部分が増えるために儲かりやすくなる」という仮説である。オープン・モジュラーとの共生のあり方として非常に面白い考察だと考える。
【オープン・モジュラー世界側の課題】
一方で、オープン・モジュラー世界の業界側でも自動車のインテグラル世界との接触や関与を強めることを検討すべきではないかと思う。
弊社を訪ねてこられる素材メーカーや電子・電機メーカーの方々の声を総合すると、長期安定的な取引が望め、高水準とはいえないものの収益性のブレが少ない自動車産業への新規参入に興味はあるが、それ以上に取引開始までの時間の長さや門戸の狭さ、自動車メーカーのコントロールの強さ・裁量範囲の小ささ、リターンの割に性能保証条件の範囲や品質管理の責任・負担が大きいことを理由に躊躇・嫌悪される企業も多いようだ。実際に家電メーカーの中には車載部門の縮小・撤退を考える企業もある。
だが、自動車ビジネスが厳しいからこそ参入の価値があるとも言える。藤本隆宏教授は「製品アーキテクチャの概念・測定・戦略に関するノート」の中で自転車用変速機のシマノの事例を次のように紹介されている。因みに自転車そのものはオープン・モジュラー型製品だが、シマノの変速機はインテグラル型製品である。非常に示唆に富んでいるのでこれもそのまま引用したい。
「シマノは、確かに、多段式のギアコンポーネントに集中し、そこで業界標準を取ることにより、『自転車のインテル』のような『アーキテクチャの位置取り』を実現している。ところが、そのシマノが、実は冷間鍛造の自動車部品も少しだけ生産している。シマノの自動車ビジネスは、予想通り『中インテグラル・外インテグラル』型であり、あまり儲かっていないという。しかし、同社によれば、自動車部品を納入し、厳しい自動車企業の要求に応えることによって、モノ作り能力が非常に鍛えられる。そこで鍛えた技術が自転車部品に転用され、自転車ビジネスの競争優位を支える。このため、あえて利益の薄い自動車部品ビジネスにも少しだけ参入しているという。」
つまり、自動車のインテグラル世界の知識・経験を蓄積したからこそ、オープン・モジュラー型の自転車業界にあってインテグラル型のものづくり、価格競争に巻き込まれない独自のポジショニング確保、高収益事業の構築に成功したということだと思われる。自動車産業に忌避感を持つ異業種企業にぜひ聞いてもらいたいメッセージである。
<加藤 真一>