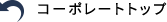自動車業界ライブラリ > コラム > 2007年に始まる新たな自動車産業史と戦略を考察する(前編)
2007年に始まる新たな自動車産業史と戦略を考察する(前編)
◆ダイムラークライスラー、サーベラスにクライスラー部門を売却。正式発表
<2007年05月14日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【時代の節目】
ダイムラーとクライスラーが合併解消という発表に時代の節目を感じた読者も多いことだろう。筆者も同感である。1998年に世界の自動車産業に合従連衡の引き金を引いたダイムラークライスラーの合併は時代の変わり目を予感させたし、現実にその翌年には日産へのルノーの出資参加と経営権取得によって世界的 M&A の波が日本にも押し寄せてきたことを日本人にも痛切に感じさせた。
そのダイムラークライスラーが三菱自工の経営から引き揚げた頃から多くの人が潮目の変化を感じていたはずだが、今回の発表によって一つの時代が完全に過ぎ去ったことを明確に意識することになったからである。
今回はこの時代の節目を踏まえて、過去日本および世界の自動車産業はいつどのような時代を経てきたのか、日本的ものづくりと欧米型ものづくりとの関係を機軸に整理してみたい。また、2007年が時代の節目だというのであれば、今回の整理を踏まえて、次回これからの時代はどのような時代になると考えられるのかという考察と、そのような時代における日本的ものづくりはどのようなものであるべきだと考えられるのかという私見を提供することとしたい。
まず、日本的ものづくりと欧米型ものづくりとの関係を機軸に据えた場合に過去の世界の自動車産業史は 4 つの時代に区分できるというのが筆者の考えである。また、この時代区分の意味合いを分かり易くするため、各々の時代に国際社会における政治外交史のアナロジー(比喩)を加えてみた。
1. 日本的ものづくりの形成期(1936~ 1966年)~日清日露戦争の時代
2. 日本的ものづくりと欧米型ものづくりの衝突期(1966~ 1988年)~世界大戦の時代
3. 日本的ものづくりと欧米型ものづくりの協調期(1988~ 1997年)~サンフランシスコ平和条約の時代
4. 欧米型ものづくりの覇権競争期(1998~ 2007年)~冷戦の時代
日本的ものづくりとは、統合的なプロセスによって品質と生産性を高めながら、市場が求める変化や多様性、コストにスピーディに対応していくものづくりの思想や仕事の進め方を指す。ややステレオタイプの嫌いはあるが、欧米型ものづくりとは少なくともその原初形態においては規模の経済(北米)や市場の価格吸収力(欧州)にものを言わせてコスト、時間、統合性に改善の余地を残した成果重視型のものづくりのことをここでは指している。
【日本的ものづくりの形成期~日清日露戦争の時代】1936~1966
この時代は自動車製造事業法によってトヨタ、日産が参入(いすゞは参入済み)した 1936年に始まり、トヨタから初代のカローラ、日産から初代のサニーが発売された 1966年までの 30年間と定義する。この期間に上述したような日本的ものづくりの原型が形成されたと考えられるからである。
戦前、国内の乗用車市場は GM、フォードの組立に独占されており、戦時中これら2社が排除された後も国産車は三輪車中心であったうえ、戦後は軍民転換により自動車メーカーが 30 社以上も乱立したが、燃料や原材料の調達に事欠いたこと、非軍事化のための財閥解体で内製部品部門が分社・解体された影響もあり、各社の稼働率は 20%台に留まった。
1950年には日銀総裁が「日本に自動車工業は不要である(海外から輸入する
方が消費者や国民経済の利益にかなう」と解き、日産はオースチンと、日野はルノーと提携してライセンス生産に乗り出すなど、日本の自動車工業は圧倒的な国際競争上の経済的不利を抱えた脆弱なところから始まっている。その脆弱性が一気に露呈したのが 1949年ドッジラインによる緊縮財政で、資金調達に行き詰ったトヨタは翌年大量の解雇を余儀なくされ、それに伴う労働争議で経営危機に陥った。あたかも開国直後の幕末の様相である。
この状況を一変させたのが朝鮮戦争勃発に伴う米軍からのトラック特需で、これを機会に日本の自動車産業は息を吹き返した。それと同時に日本メーカー各社は過去の反省に立って、安定的な供給や品質を確保するための系列の構築、在庫や稼働率の変動に泣かされないための後工程引き取り方式、軍用機産業に倣った効率的な製品開発組織である主査制、二度と労働争議に見舞われないための終身雇用慣行の導入に乗り出している。その後、1955年には国産乗用車第一号のクラウン、1959年には軽乗用車スバル 360 が発売され、1965年にはトヨタがデミング賞を受賞している。
今日の日本的ものづくりの原型が形成されたのは正にこの時期で、1966年のカローラ、サニーの登場によってほぼ完成したといえる。
日本的ものづくりは当初から海外指向であり、1957年には早くもクラウンの対米輸出が行われた。富国強兵による国作りを目指した明治期の日本の姿に重なるが、この頃までは米国メーカーも日英同盟宜しく合弁、技術指導等を通じて日本的ものづくりの形成とその海外進出を間接的に支援した。1963年の独チキンタックスへの報復で VW のピックアップを駆逐したようにこの頃まで米国車の仮想敵国は欧州車であり、日本車はライバルに値しない存在であったということもあろう。朝鮮特需を明治維新、クラウン発売を日清戦争、カローラ、サニー登場を日露戦争に準えることができると思う。
【日本的ものづくりと欧米型ものづくりの衝突期~世界大戦の時代】1966~1988
日露戦争の勝利直後から日米関係が険悪化したのと同様に、カローラ、サニーの登場直後から日本的ものづくりは米国との摩擦を起し始める。1969年に対米進出して大成功を収めた日産 240Z が日本車に対する米国の見方を一変させ、1970年のマスキー法、1973年の第一次石油危機への対応に米国車が手をこまねいている間に 1972年にホンダがシビック CVCC を投入して課題を一気に解決したことで一躍日本的ものづくりは欧米型ものづくり世界で脚光を浴びる。
低燃費と低価格を武器にした日本車は集中豪雨的に対米輸出され始め、業績や財務体質を一気に強化した。1979年の第二次石油危機をきっかけに翌 1980年には日本が自動車生産世界一となった。
この辺りから日本的ものづくりは米国車の脅威とみなされて政治問題化することになる。翌 1981年には米国でローカル・コンテンツ法案が通過し、日本側は輸出自主規制で摩擦を回避しようとするが、一触即発の状態はその後も続き、ようやく緊張緩和の兆しを見せるのがホンダ・オハイオ工場、日産スマーナ工場、トヨタ GM 合弁(NUMMI)など日本車各社のグローバル化(現地生産の開始)と 1985年のプラザ合意による円切り上げ、それらを通じた日本車の対米輸出ペースの鈍化と米国メーカーの価格競争力や業績の回復によるものだった。最終的には 1988年のトヨタケンタッキー工場設立によって日米衝突は一応の決着を見る。
欧州でも同じ時期に同じような経過を辿る。欧州各国は日本車の輸出先が北米から欧州にシフトされることを恐れて日本車輸入枠を設け、1985年には輸出規制も始まる。問題がほぼ決着するのは 1986年に英国日産が生産を開始して以降である。
欧米的ものづくりが石油危機で疲弊する中で、それを契機に逆に自動車大国に上り詰めた日本的ものづくりは第一次大戦後の日本の姿と重なる。危機を覚えた欧米型ものづくりは、グローバル化と為替切り上げで原初日本的ものづくりの競争優位の根源を叩いたという整理になり、第二次大戦の経過に対比できる側面がある。
【日本的ものづくりと欧米型ものづくりの協調期~サンフランシスコ平和条約
の時代】 1988~ 1997
ところが、グローバル化と為替によって潰したはずの日本的ものづくりは、増加の勢いこそ失ったものの引き続き顧客の支持を得て獲得した地盤を失うことはなかった。低燃費、低価格といった顕在的な強みの深層に、統合的なプロセスによる品質と生産性の高さに潜在的な強みを持っていた。1989年のレクサス対米展開の成功によってこの強みは顕在化し、これ以降日本的ものづくりは統合性を武器にする形に進化する。
日本的ものづくりの壊滅に失敗したにも拘らず、欧米型ものづくりと日本的ものづくりの関係は 1966年以降で最も安定した。
その背景には、
(1)石油価格が下落して大型米国車の人気が復活し、1963年の報復関税以来、輸入車に対して高い関税障壁を維持していた商用車セグメントが勃興してきた結果、ビッグ3の業績が回復してきたこと、
(2)日本車の現地生産が増加するとともにバブル時代には日本車メーカーも内需に注目した結果、自主規制枠を使い切れないくらいに日本車の対米輸出が減少したこと、
によってビッグ 3 側に余裕が生まれたことが上げられる。
寧ろ、
(3)キャプティブ・インポート(日本車の米国車ブランドでの OEM 輸出)や日本メーカーとの提携によって日本的ものづくりから恩恵を得たり、学んだりすることの方が効果的だと考えられるようになったこと、
(4)その結果、90年代初めには少なくとも定量的な指標において日本車との品質や生産性のギャップが殆どなくなったこと、
(5)さらにバブル崩壊後は多くの日本車が業績不振に陥り、欧米型ものづくりにとっての脅威が減少したことも影響している。こうした背景から 1994年には対米輸出自主規制が撤廃される。
つまり、この時期、日本的ものづくりは、前半は学習や利用の対象として、後半はどちらかといえば反省の対象とみなされ、いずれにしても国際的な脅威とはみなされなくなった。サンフランシスコ平和条約調印後の日本の姿と重なるところがある。
しかし、この時期に日本的ものづくりも裏側では進化と同時に、欧米型ものづくりに学んで大幅にその刷新に取り組んでいた。1992年にはトヨタが、1994年にはホンダが、製品開発組織を再編するとともに、各社とも標準化・共通化によるコスト革新を行なって環境変化に内側から備えていた。その成果が 1997年末のハイブリッド専用車プリウスになって現れるが、欧米型ものづくり側ではその意味合いや影響にそれほど注目していなかった。
【欧米型ものづくりの覇権競争期~冷戦の時代】1998~2007
一面的とはいえ日本的ものづくりへのキャッチアップを負え、業績も安定してきた欧米型ものづくりの間では覇権競争が開始された。その引き金となったのが独ダイムラーによる米クライスラーの事実上の吸収合併である。
欧州企業は、日本的ものづくりの台頭以降、世界自動車産業史においてリージョナル・プレーヤー的な存在に過ぎなかった。だが、次世代の戦場は環境・安全技術になると想定し、そこでの成功要因は当該技術の開発に必要な経営資源の獲得と、開発した技術を実質的な業界標準化するための業界内のポジションの確保になると定義していた。そこで、日本的ものづくりの退潮期に満を持してスーパーパワー化を狙って動き出したものと捉えられる。ダイムラーは直前に A クラスを発表してフルラインメーカー化の意思も明確にしている。
これに対して米国側もブランド力のある老舗欧州企業の買収という形で反撃に転じる。欧州にあって米国にないものがブランド資産であり、次世代の戦場はものづくりではなく、ブランドとバリューチェーンが舞台になると想定しての行動である。ボルボ、ジャグアー、ランドローバー、アストンマーチンといったブランドが米国企業の傘下に入っていく。
次世代の戦いの構想に欧米間で違いはあるものの、いずれにせよ「箱の中身よりもまず箱を確保することが重要だ」という認識で大型の M&A が展開された。あたかも冷戦期にイデオロギーを異にする米ソが核抑止力を用いて世界分割競争を展開したように、世界自動車産業においても M&A という飛び道具を用いた覇権争いが展開されていくのである。
日本的ものづくりも多くが覇権競争の対象とされた。覇権競争の対象にはならなかったトヨタ、ホンダですら覇権競争の主役側に回ることはなかった。この期間、日本的ものづくりはその前の期の負債の処理に追われ、覇権競争に主役的な立場で参画する道を閉ざされていたのである。
多くの日本車メーカーは、箱を確保する側に回れなかった代わりに箱の中身の充実に努めた。経営資源を蓄積し、統合的なものづくりプロセスの品質、コスト、スピードの向上に充てることで小さくても存在感のあるリージョナル・プレーヤーとして生き残ることを目標とした戦略を取ったのである。
その結果、商品開発面では乗用車派生の SUV やピックアップ、ミニバン、クロスオーバーなどに活路を見出した。市場開拓面では成長前の中国への進出(1999 広州ホンダが最初)、1997年のアジア危機で疲弊したタイの輸出基地化、マザーカー、マザープラントなしで生産準備以降の全プロセスを現地に権限委譲するプロジェクト(トヨタ IMV)などを推進していった。プリウスも先代の市場経験をしっかり織り込んだ 2台目が登場する。
この時期、次世代戦争を睨んだ箱の確保に出遅れた反面、箱の中身で欧米型ものづくりに先行したことの意義は大きい。
自動車産業における冷戦期は現実世界とは異なる経過で終結する。現実世界では、資源に劣るソ連が米国との 40年以上もの戦いを維持するコストに耐え切れなくなり、兵糧攻めのような形で敗北し、米国が唯一のスーパーパワーとして君臨する時代を迎える。ところが、自動車産業においては米国も欧州もいずれも体力を疲弊してしまい、次世代戦争が始まる前にメインプレーヤーの座から降りていくことになったのである。
そして入れ代わりに唯一のスーパーパワーとなったのが、こつこつと経営資源の蓄積と統合的プロセスの進化・刷新に努めてきた日本的ものづくりである。トヨタは売上高、販売台数で GM を抜くと見られ、利益額では既に世界最大となった。他の日本車メーカーも多くの国内工場はフル稼働状態にあり、軒並み史上最高益を更新している。今や世界で生産される自動車の3台に1台が日本車になっている。前の時代の始めには誰も予想できなかったことだが、日本的ものづくりが覇権を握る形で新時代を迎えることになったのである。
(後編に続く)
<加藤 真一>