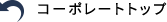自動車業界ライブラリ > コラム > 少子高齢化時代の製品開発哲学
少子高齢化時代の製品開発哲学
◆小糸製作所、白色LEDヘッドランプを「レクサス LS600h」で実用化
<2007年3月27日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【世界で最も製品開発に拘りのある自動車メーカーはどこか】
こういう質問を受けると多くの人が、水平対抗エンジンや RR レイアウトに固執するポルシェとか、直列 6 気筒エンジンや 50:50 の重量配分に拘り続ける BMW を上げることだろう。
だが、製品開発に最も強い拘りを持っているメーカーは実はトヨタではないかと筆者は考える。
確かにトヨタは特定の技術やアーキテクチャーに固執してはいない。他社がV6 を採用する中、直列 6 気筒を貫いてきたクラウンやマーク X は現行型できっぱり V6 エンジンに置き替えたし、FR スポーツとして人気のあった AE86 型レビン・トレノを次世代であっさり FF に切り替えた歴史もある。
では、何がトヨタの製品開発上の拘りかといえば、新技術採用の原則への拘りだと考える。トヨタの新技術採用には次の原則があると筆者は考えている。
1. 最高級製品こそが技術的に最もチャレンジングでなければいけない。
2. 最高級製品での採用だから、どんな犠牲を払っても新技術の完成度を極める。
3. 最高級製品でしか採用の余地がない新技術は採用してはいけない。
今回、トヨタはレクサス LS600h に小糸製作所が日亜化学の白色 LED を使って開発した世界初の LED ヘッドランプを採用した。
従来、LED はレスポンスの早さ、電力消費量の少なさ、交換が事実上不要なほどの長寿命であること等のメリットが指摘されながら、光量や輝度の問題からヘッドランプへの採用は困難だ言われていた。
特殊な素材や光合成方法、冷却構造を使って問題を解決した上で、逆に世界最高水準の明るさを確保したとのことである。
最新技術は最高級車から搭載するという上記の原則 1 が当てはまる。そして、おそらくこの LED ヘッドランプでも上記の原則 2、3 も踏襲されることは間違いないだろう。
完成度を極めたと判断できるまで工数を掛けてあらゆる問題を潰した上での採用であろうし、最終的には B ・ C セグメントまで含めた全ての車種に展開していく展望を持った上での採用であったはずである。
トヨタではこの新技術採用の原則が適用された事例は枚挙に暇ない。
例えば、「デュアル VVTi」 (吸排気可変バルブタイミング機構)。最初は1998年にアルテッツァ(現レクサス IS)で採用されたものが、昨年 10月発売の現行カローラ(アクシオ)にまで展開された。
1998年にプログレで初採用した「NAVI ・ AI-SHIFT」(HDD カーナビ協調 CVT)も同じく現行カローラに搭載されている。
現行カローラではプリクラッシュ・セーフティやインテリジェント・パーキング・システムも選択可能になっている。1989年にセルシオ(現レクサス LS)が初採用したオプティトロン・メータも今では幅広い車種が採用しているし、トヨタ車の半数以上が車載カメラを装着する。
他社の新技術採用の原則もそれほど違うものではないだろう(もっとも中にはクレームが出てもブランドに与えるイメージの小さい下位セグメントから新技術を採用するという原則の会社もあるようだ)が、原則の徹底ぶりが異なる。
例えば、4WS、ミラーサイクル。元々全車種展開する展望があって採用されたものではないと思われるし、実際に特定車種での単発採用で終わった。
GDI は全車種展開の戦略の元に開発・採用されたはずだが、完成度を極めないままに採用・展開されたために多くのクレームを受けて消えていった。
トヨタの新技術採用の原則は、その徹底ぶりに拘りがあり、その拘りぶりは「製品開発哲学」とも呼べる領域にあると考えられるのである。
【トヨタの製品開発哲学の経済的意味合い】
上記の哲学を経営学的・経済的に分解すると次のロジック、サイクルになると考える。
1. 新技術採用の取り組みは常に最高級製品から行なう。
2. 最高級製品のコスト吸収力を活用して新技術の完成度を極める。
3. 他の装備や価格、宣伝、店舗網などを通じて最高級製品の競争力を高める。
4. 最高級製品の競争力を活用して新技術の開発費と設備投資の償却を進める。
5. 最高級製品の市場経験をナレッジ DB 化して「論理関数的な標準」*を作る。
6. 「論理関数的な標準」に基づき新技術の転用開発を進める。
7. 償却済みのコスト競争力を活用して量販製品に新技術を転用する。
8. 競合車より早く安く採用(転用)した新技術で量販製品の競争力を高める。
9. 量販製品のボリュームがもたらす収益を活用して、上記 1.を行なう。
*「論理関数的な標準」とは、ある技術の設計パラメータを固定して設計標準とするのではなく、同じ機能・性能や品質を得るのに必要な縦横比だとか素材混合率などの公式を見付け出して、それを設計標準とすることをいう。
この標準を使えば、「小さなスペースに収めるためにある部品の縦の長さをこれだけ短縮したら横の長さの最適解はいくつか」といった設計課題に柔軟かつ迅速に対応できることになり、機能・性能や品質を維持しながら設計の生産性を高めることが出来る。
つまり、トヨタの最高級車は、新技術の採用の可否の検討の場、完成度を高める場、償却費を稼ぎ出す場、設計標準を確立する場として活用され、利益は最高級車で実証済みで償却済みの技術を同セグメントの競合車よりもいち早く採用して商品性対価格競争力を高めた量販車によって得る、という構図である。
【トヨタの製品開発哲学にいま注目する意義】
筆者が「いま」あらためてトヨタの製品開発哲学に注目する理由は、次の 2点で重要な示唆を含むと考えるからである。
第一に、少子高齢化時代の日本に求められる社会構造
第二に、新興国が台頭する国際社会で日本が取るべき世界戦略
この 2 点について順番に述べていきたい。
【少子高齢化時代の日本に求められる社会構造】
<日本のミドル・シニアエイジの変化>
VERY、STORY、UOMO、OCEANS、GOETHE、ZINO、LEON。
何のことかお気づきだろうか。最近書店の雑誌コーナーのかなりのスペースを占拠している雑誌のタイトルである。
これらの雑誌には一つの共通点がある。「リッチなミドル・シニアエイジのための優雅でお洒落なライフスタイルや消費行動の提案」を標榜している雑誌だということである。
日本のミドル・シニアエイジをその前後の世代と比較した場合に顕著な属性は、「裕福で成熟した消費者」だということではないだろうか。
オールナイターズ・おにゃんこクラブの前後の世代で TV で見る空想の世界と日常の現実世界の間に境目を感じずに育ち、学生時代や入社後間もない時期に DC ブランドブームを経験し、バブル経済真っ只中に消費生活入りして海外あちこちを見聞し、世界の一流品を見る眼も養った。
若者たちが就職冬の時代に入ってフリーター・ニートとなって下流社会入りしている間に、どちらかといえば格差社会の勝ち組の側に回ってそこそこ余裕も生まれてきた。
一方で、価格破壊の過程でユニクロのような安くても質のよい商品が存在することも学んだ。
だから、今はこれみよがしの高価格品をありがたがることはないが、質やセンスのよい商品やサービスには出費は惜しまない。そういう世代である。
筆者は今年から週 2 回都心のスポーツジムに通い始めたのだが、そこに来ている人たちの多くも予想に反して美容目的の若い女性たちではなく、ミドル・シニアエイジである。
しかも、必ずしもメタボリック症候群やその予備軍の体型の人たちではない。
想像だが、優雅でお洒落なライフスタイルや消費行動を持続するための健康や体力への内面投資を目的にした人たちと映る。
一方、筆者は時々外部のセミナーや社会人講座に聴講者側で行ってみるのだが、そうした席も自己啓発目的のミドル・シニアエイジで溢れている。これも一つの内面投資である。
内面投資のリターンは株式投資や外貨預金ほど期待値が明確ではないし、貴金属や豪邸のように他人に財産や所得を見せ付けられる要素もない。
それでも内面投資を行なうミドルやシニアが多いのは、多くのミドル・シニア向け雑誌がキャッチフレーズにしているように「リッチを誇んな、センスで光れ」、「必要なのはお金じゃなく、センスです」ということなのだろうと思う(中には逆の中身になっているような言行不一致の雑誌もあるように見受けられるが)。
<日本の社会構造の変化>
実際には「センスで光る」ためにはそこそこの「お金」が必要である(少なくとも雑誌で推奨されているような「センス」の発揮には相当の「お金」を必要とする)。
ということは、元々「お金」の面で若年層よりも優位な立場にあるミドル・シニア層は「センス」の面でも潜在的優位な立場にあり、そのポテンシャルが顕在化した場合には、経済のみならず文化の面でもミドルやシニアが主導権を持ち、発信源になっていく社会構造への変化の兆しが生じているのではないかと思われる。
そして、この変化は別に懸念すべきことでも恥ずべきことではないはずだ。
少なくともバブル崩壊後 10 数年の日本は長らく子供たちにとって憧れの大人がいない社会、一生子供のままでいたい社会、成長や成熟を嫌悪・拒否したくなるような社会だった。
リストラに怯えて元気や勇気を失った大人たちの姿、お洒落にも内面投資にも縁遠いライフスタイルや消費行動の大人たちの姿ばかりを見て育ってきた子供たちがそう思うのも無理はない。
一度しかない人生の花の時期を刹那的で享楽的に過ごそうとする走る子供たちが世に蔓延し、彼らの価値観や行動が唯一の文化の発信源となって、大人たちはそれを追認したり、迎合したりするだけの受動的で脇役の存在に過ぎないという社会であった。
それはそれでアニメや J-POP など「Japan Cool」と呼ばれる日本のソフトパワーの源泉として評価すべき側面も大きいが、未来や QOL (質の高い生き方)への投資を失った社会には展望がない。
2 週間前の本誌「AYA の徒然草」の表現を借りれば、「人の旬」が若いときの一度しかない社会構造がこうした現象を産んだとも考えられるのである。
これに対して、大人がもう一つの文化の発信源となって、未来や QOL 等への内面投資も含めた優雅でお洒落なライフスタイル、消費行動を送っている姿を子供たちに見せてやることができれば状況はかなり異なったものになってくるのではないだろうか。
子供たちが成長して成熟した社会の一員になることに夢、憧れ、喜び、誇りを感じられる社会構造、「徒然草」風に言い換えるならば、何度でもいつまでも「人の旬」がある社会構造となり、成長や成熟へのモチベーション、未来やQOL への投資の動機付けが社会に浸透していくのではないかと思う。
少子高齢化時代の日本の社会では一人ひとりの生産性を高めることが存続条件となる。そのときに成長や投資への強いモチベーションを有した社会構造が出来ていれば、この存続条件はそれほど高いハードルではなくなるだろう。
トヨタは、最高級車において今回の LED ヘッドランプやプリクラッシュ・セーフティやハイブリッドのような最新の技術的チャレンジを、これ見よがしにではなくさらっとだけ見せる(過剰な装備インターフェースや情報を提供することなく、必要なときに必要なだけマシン側で機能を発揮する)やり方で、優雅でお洒落な大人の世界の文化の発信源たろうとしているのではないだろうか。
それと同時に、時差を置きながら製品ラインナップ全体への普及に努め、最終的には社会全体が同じ価値を手にすることができるようにしようという品格も忘れていない(と信じたい)。
【新興国が台頭する国際社会で日本が取るべき世界戦略】
他の全ての産業と同様、自動車においても汎用部品をかき集めてきて、安い賃金を使って低コストで組み立て、安値で売るというものづくりでは途上国に勝てないし、今後益々一人ひとりのモチベーションや生産性の高さが求められる日本の社会構造にも向いていない。
だからといって、高額品・高級品だけに特化したものづくりでは全体にその効果が行き渡るほど日本の経済規模は小さくない。北欧やベネルクスのような国々とは違うのだ。
トヨタの製品開発哲学はこのジレンマに一つのヒントを与えてくれるように思うことが、「いま」同社の哲学に注目するもう一つの理由だ。
今一度、トヨタの製品開発哲学の経営学的・経済的意味合いを眺めてみよう。
1. 新技術採用の取り組みは常に最高級製品から行なう。
2. 最高級製品のコスト吸収力を活用して新技術の完成度を極める。
3. 他の装備や価格、宣伝、店舗網などを通じて最高級製品の競争力を高める。
4. 最高級製品の競争力を活用して新技術の開発費と設備投資の償却を進める。
5. 最高級製品の市場経験をナレッジ DB 化して「論理関数的な標準」を作る。
6. 「論理関数的な標準」に基づき新技術の転用開発を進める。
7. 償却済みのコスト競争力を活用して量販製品に新技術を転用する。
8. 競合車より早く安く採用(転用)した新技術で量販製品の競争力を高める。
9. 量販製品のボリュームがもたらす収益を活用して、上記 1.を行なう。
これを要約すると次の構図になることも既に述べた。
「トヨタの最高級車は、新技術の採用の可否の検討の場、完成度を高める場、償却費を稼ぎ出す場、設計標準を確立する場として活用され、利益は最高級車で実証済みで償却済みの技術を同セグメントの競合車よりもいち早く採用して商品性対価格競争力を高めた量販車によって得る、という構図である。」
日本全体でこのサイクルや構図を築き、維持することができれば、日本製品は、高級品であれ普及品であれ、常にどのセグメントにおいて世界一の商品性対価格競争力と経済規模を保つことになり、途上国との価格競争に巻き込まれることも、高級品のみに依存した小規模経済に陥ることもないだろう。
急速に近隣国・途上国が発展を続ける一方で、日本では人口減少が GDP と歳入を縮小させ、ODA や国連分担金など外交予算の削減の削減を余儀なくされ、その結果、日本は国際社会での相対的プレゼンスを急速に落としていくのではないかと危惧されている。
しかし、上記のようなサイクルで世界と向き合い続ければ、人口が減っても国際競争力の喪失や経済規模の縮小を最小限に留め、世界戦略遂行のためのリソースを維持できる可能性が高まるから、日本の未来の国際的プレゼンスを極端に悲観する必要はなくなってくる。
トヨタの製品開発哲学にいま改めて共鳴する理由は、この世界戦略上の示唆を感じる点にもある。
<加藤 真一>