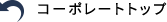自動車業界ライブラリ > コラム > 自動車産業への新規参入希望者は自動車メーカーの中間決算から何を読み取るべきか<後編>
自動車産業への新規参入希望者は自動車メーカーの中間決算から何を読み取るべきか<後編>
◆トヨタ、グループでの 2007年世界販売計画、940 万台前後で最終調整
<2006年11月28日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先週の前編に引き続いて、自動車産業への新規参入者の立場に立って、トヨタ・日産・ホンダ三社の事業の構造、戦略、課題の違いを中間決算から抽出していきたい。前編では、ROA (総資本利益率)を構成する三つの要素のうち、(1)資源配分の状態、(2)資源活用の度合いの 2 点について触れたので、後編の今回は(3)資源活用の効率を分析し、3 社の違いをまとめたうえで、新規参入者の視点に立って各々へのアプローチ方法を考察していくことにする。
【前編のおさらい】
ステークホルダー(経営資源の提供者)から調達してきた一次経営資源(カネ)を、何(二次経営資源=4M=ヒト、モノ、コト)に、どれくらい使うか、というのが「資源配分」の問題であった。その考察を通じて分かったことは次の通りである。
・トヨタは、系列投資、設備投資(グローバル)への使い道が多く、人的投資、開発投資、金融投資は少ない。
・日産は、人的投資(日本)、開発投資、金融投資への使い道が多く、系列投資、設備投資は減らしている。
・ホンダは、系列投資、人的投資、開発投資、金融投資への使い道が多く、設備投資(北米)は増やしているがまだ少ない。
また、4M (ヒト、モノ、コト)を、最大のステークホルダーである顧客が価値を認識できる製品(モノ)に転換することが企業の設立目的である。どれだけの顧客価値を産み出したかの尺度が売上(カネ)であり、売上(カネ)は他のステークホルダー(サプライヤ、ディーラー、従業員、社会、投・融資家)へ成果配当の総原資だから、企業は出来るだけ売上(カネ)を早く大きくするように知恵と汗を絞る。それが「資源活用の度合い」の問題であり、生産性の問題である。その考察を通じて分かったことは次の通りである。
・トヨタは、三大営業資産の生産性が良好で人的投資の生産性も高いが、系列投資は開発費削減に効果を発揮しているが、必ずしも期近の売り上げに直結していない。地域的には日本と欧州の生産性が比較的高く、北米・アジア・その他にやや課題を残している。
・日産は、系列投資の生産性は高いが、三大営業資産(特に有形固定資産)と人的投資の生産性改善が急務になっている。地域的には北米と欧州の生産性は比較的高いが、日本とそれ以外の地域の生産性が低い。
・ホンダは、三大営業資産、系列投資、人的投資ともトップレベルの生産性を誇るが、設備に依存しない形での生産性向上が上限に達しつつある。地域的には北米の生産性が低く、他の地域が軒並み高い。
【資源活用の効率】
<効率の概念>
自動車メーカーが持続的に第一のステークホルダーたる顧客に対して価値あるモノを産み出し続けていくためには、価値の尺度であり、他のステークホルダーへの成果配当の総原資である売上を大きくしていかなければならないことは前項で述べたとおりである。
だが、ステークホルダーは利害を共有する面とお互いに利益相反の関係に立つ面の両方があるから、経営はステークホルダー間での成果配当のバランスにも気を配らなければ持続的な資源供給を受けられなくなる。
例えば、売上の 7~8 割は売上原価として、サプライヤや社内の開発・製造現場への配当に回るので、そこに回るカネがあまりに多い(原価率が高い)と、他のステークホルダーに回るカネ(間接従業員の給与、銀行への返済資金、税務署への納税額、株主の純利益)が少なくなる。長期的には彼らから経営資源供給を受けることが難しくなり、モノづくりに支障を期すことになる。
逆に、サプライヤや現場に回すカネを減らせば、他のステークホルダーの取り分は一義的には増える。だが、長期的にはサプライヤや現場から価値あるモノづくりに必要な経営資源の提供を受けられなくなり、顧客価値の尺度である売上が低下し、売上はステークホルダーの取り分の総枠であるから、それが低下すると結果としてステークホルダー全体の利益を損ない、経営資源供給を受けられなくなり、やはりモノづくりに支障が出る。
つまり、全てのステークホルダーに対して、貢献度に見合った公正な成果配当が為されるように意を用いることが持続的モノづくりには不可欠であって、そのことをここでは「効率」(「生産性」と類義語だが同義語ではなく、寧ろ「最適化」に近い概念)と称しているのである。
なお、投融資家や社会への成果配当の効率まで見る場合には税引き後の最終利益までの配当を検証するべきであろうが、誌面の都合もあり、また最終利益までには営業外・特別損益など本業以外の他の要素が入り込んでしまうこと、営業利益以降の成果配当(借金返済額と納税額と最終利益)は経営の意思とは関わりなく半自動的に決定してしまうことから、ここでは営業利益までの配当の効率を見ていくことにする。
<原価率>
トヨタ 80.4%、日産 76.2%、ホンダ 76.3%。
上半期の各社の売上高に対する売上原価の比率(連結ベース)である。(ホンダは研究開発費を売上原価にも販管費にも組み入れず独立の勘定として いるが、ここでは便宜的に全額を売上原価に組み入れた。)
売上原価には、原材料費(部材購入費)、直接員の人件費、設備の減価償却費、研究開発費、その他開発・製造工程の経費が含まれる。
つまり、原価率とは、サプライヤと社内の現場(開発・製造部門)への配当率である。
既に見てきたとおり、トヨタの研究開発費の割合は 3 社中最も低く、設備投資が多いとはいえ現時点での減価償却費は意外に低い(売上高の 4.0% であり、日産の 7.8% に比べたら格段に低い)。
また、規模の経済が働き、ベンチマーキングにも熱心なトヨタの部材購入費や経費が突出して高いとは考えにくい。
とすると、考えられるのは、現場(直接人員)への配当率の高さである。もっとも、トヨタの従業員の平均給与(単体の数字なので参考値でしかないが)はホンダの 820 万円を下回る 805 万円に過ぎないから、人件費単価が高いのではなく、間接人員に比べて相対的に直接人員の割合が高いのではないかと推察される。
つまり、「主査制」、「センター制」などを通じて、現場への権限委譲と、現場での自己責任・自己管理(いわば現場の「自働化」)が進んでいるためではないかと考えられるのである。
後工程で本社のスタッフ部門が管理・牽制するのではなく、現場が工程内で標準に基づき「自働的」に早い段階から問題の抽出と解決と文書化に努める結果、どうしても現場の管理負荷が高まる。そこに集中的に配当した結果が原価率の高さに現れているのではないかと思われる。
<販管費率>
トヨタ 10.1%、日産 16.1%、ホンダ 16.1%。
同じく上半期の各社の売上高に対する販売費および一般管理費の割合(連結ベース)である。
販管費には、間接人員(本社スタッフ部門等)の人件費やオフィスの賃料等の管理費用や、広告宣伝費や販促奨励金などの営業費用が含まれる。
つまり、販管費率とは、社内の非現場部門や社外のベンダーへの配当率だと読み替えることができる。
ここでは売上原価とは逆にトヨタの数字が日産・ホンダに比べて 6 ポイントも低い。日産・ホンダの数字もかつてより低下しているが、トヨタも低下しているので、過去 10年間一貫した構造的なギャップが存在する。
しかも、本年上半期にトヨタは販売金融事業で金利スワップ取引の時価評価損を計上しているから通常よりも販管費率が高めであったにも拘らず、である。
《トヨタ》
つまり、トヨタの社内の非現場部門や社外のベンダーへの配当率は他の二社よりも低いということになる。こちらの要因は原価の逆、つまり標準化とフロントローディングの結果だと見るべきだろう。
現場に権限を委譲し、現場の自働化を進めようとすれば、管理標準が明確に定められ、現場が管理標準に基づく自律的管理によって問題を早めに潰しておく「仕組み」ができていなければならない。
また、営業部門においても、バリュー・チェーンの最終工程(販売の最前線)の「仕掛け」で売る(Selling)のではなく、前工程(製品、価格、流通、販促のミックス)の「仕組み」で売れる(Marketing)形が出来ていなければこうはならない。
つまり、標準化とフロントローディングを進めた結果として、現場への権限委譲と現場の自働化が進み、直接人員の負荷(原価率)は高くなるが、反面、本社部門やバリュー・チェーンの最終工程の負荷(販管費率)が下がっているのではないかと読み取ることができる。
現場への配当率を高めて、非現場部門やベンダーへの配当率を下げることに効率を求めているのが、トヨタの「仕組み」だと映るのである。
《日産》
日産の場合は、系列投資が少なく、自社開発を余儀なくされるうえに設備の償却費も高いのに原価率が低いということは、現場やサプライヤへの配当率を低く抑えているということになる。
一方、販管費率が高いのは、製品開発プロセスで「コミットメント制」と「合議制」を取っていることや、設備や人の生産性が停滞していることが影響していると考えられる。
つまり、現場に全体を仕切る権限を持つリーダー(主査)や全社の技術資産全体を見渡すことの出来る位置にいる組織(センター)が不在のために関係者の利害調整を必要とし、スタッフ部門を厚く持たざるを得なくなる。
また、設備や人の生産性を向上させるために売上台数を稼ぐ必要があり、そのためにバリュー・チェーンの最終工程での営業費用が増加しがちである。
現場やサプライヤへの配当率(原価率)は下げながら、組織全体のボトルネックやバラつき解消のための非現場部門やベンダーへの支出(販管費率)は惜しまないというのが、日産流の効率追求の「仕組み」だと考えられる。
《ホンダ》
一方、ホンダは、系列投資は主に設備投資を抑えることに活用し、製品開発は自社開発中心である。また、製品開発プロセスで「タスクフォース制」と「地域マトリクス制」を取る。
前例や制約条件に囚われずに時間軸や地域軸で最適なものづくりを行なう体制だから、現場やサプライヤへの配当率は高まりがちである。
それでも原価率が低いのは、系列投資を活用して設備投資負担を抑えていることに加えて、トヨタほどには現場に対して全社やグローバルでの全体最適化のための管理負荷(標準化、自働化など)を負わせていないためと考えられ、その分本社部門の負荷(販管費率)が上がっているのだと推察される。
現場やサプライヤへの配当率は維持しながらも、非現場部門への配当率も高めに維持しているのが、ホンダ式の効率追求の「仕組み」であることが分かる。
このように効率追求の「仕組み」は三者三様である。だが、標準化とフロントローディングを進めて現場への権限委譲と自働化を進めているトヨタが、原価率では 4 ポイント不利だが、販管費率では逆に 6 ポイント優位に立ち、営業利益段階(投融資家や社会への配当原資)では 2 ポイント優勢だという事実は注目に値する。
<地域ポートフォリオ>
地域別の売上高営業利益率(内部取引を含む)は次の通りである。
・トヨタ:
国内 11.3% 海外 6.2% (北米 6.9%、欧州 5.1%、アジア 6.2%、その他 4.8%)
・日産:
国内 6.1% 海外 5.9%(北米 7.3%、欧州 3.4%、その他 4.9%)
・ホンダ:
国内 5.2% 海外 6.7%(北米 7.3%、欧州 2.4%、アジア 6.3%、その他 9.8%)
上記から読み取れることは以下の点である。
1.トヨタと他の二社の利益率の差は国内に起因し、海外全体での各社の差はさほど大きなものではない。
2.各社とも海外では北米の利益率が大きく、欧州の利益率が低い。
3.トヨタとホンダはアジア(ホンダは南半球でも)で稼いでいるが、日産はそこで稼げていないために他の二社にリードを許している。
4.日産は国内外の営業利益率のギャップが最も小さい。
5.ホンダは内外の利益率が唯一逆転している。
以上を総合すると、各社の課題は次の通りとなる。
・トヨタは、現場への配当率を高めて、非現場部門やベンダーへの配当率を下げる「仕組み」を取っている。この「仕組み」は国内では多大な成功を収めているものの、海外ではまだその「仕組み」が展開できていないか、できていたとしても国内ほどには成功しているとはいえない。
・日産は、現場やサプライヤへの配当率を下げて、非現場部門やベンダーへの配当率を高める「仕組み」を取っている。この「仕組み」は、国内外のバラつきが小さいバランスのいい仕組みだが、その絶対値が低いことと、欧州とアジア・その他では「仕組み」化が遅れていることが課題。
・ホンダは、現場やサプライヤへの配当率を維持しながら、非現場部門への配当率も維持する「仕組み」を取っている。この「仕組み」は、地域ごとのバラつきが大きく、北米やアジア・その他では成功しているものの、国内と欧州では成功しているとは言い難い。
【三社の相違点】
これまで見てきた資源配分の状態、資源活用の度合い、資源活用の効率を整理すると、各社の相違点は次の通りに要約される。
《トヨタ》
・厚めの系列投資によって開発投資の生産性を高め、持続的な設備投資によって人的生産性を高めるなど資源配分のバランスが取れている。地域的にもバランスよく資源配分を行なっている。
・資源活用の度合いも高く、経営資源を売上に転換する生産性の高さは群を抜いている。
・現場への配当率が高く、非現場部門やベンダーへの配当率が低い「仕組み」は、完成度が高く、国内では圧倒的に成功している。
・系列投資が短期的な売上には結びついていないことと、海外では国内の「仕組み」のヨコテンが出来ていないことが課題なので、系列投資の選別と、海外での「仕組み」(系列システム)の強化の方向性が望ましい。
《日産》
・系列投資と設備投資を削って、自社開発・アウトソーシング型路線を明確にしている。
・だが、設備と人の生産性にまだ課題を抱えており、地域的には日本と非欧米市場の生産性が低い。
・効率追求の「仕組み」は安定的だが、その絶対水準が低いことと、日米以外での「仕組み」化の遅れが課題。
・設備と人の生産性には改善余地があるので、台数増によって固定費や営業費用(販管費率)を下げ、現場やサプライヤへの配当率を上げて「仕組み」の絶対水準を上げる方向性が望まれる。日米以外の市場が優先課題になる。
《ホンダ》
・系列投資を活用して設備投資への資源配分を最小限に抑え、その分を製品の自社開発に回している。地域的には北米に傾斜配分している。
・設備と人の生産性は極めて高いが、上限に近づいていると考えられる。また北米の生産性は他の地域ほどに高くない。
・現場に管理負荷を負わせず、設備投資負担も系列に依存するやり方で、現場やサプライヤへの配当率を維持しながら、非現場部門への配当率も高めに維持する「仕組み」は、地域ごとのバラつきが大きい。
・設備・人材は限界に来ており、単価を高める方向性で特に日欧で「仕組み」の絶対水準を高めることが期待される。
【新規参入者へのインプリケーション】
このように三社間に製品開発の構造や戦略、課題の相違が見られるということは、開発品の性格やステージごとにどこの自動車メーカーに提案するべきかという適性も自ずと異なる(あくまで程度問題ではあるが)ことを示唆している。ここでは、大まかに適性分けをしてみることにする。
<開発品の価値・効用>
・高性能:ホンダ
設備・人材の限界から単価向上を課題としている。特に日欧市場が重要。ホンダ・ブランドでの単価向上は難しいと思われるので、アキュラに絞った提案も有効と考えられる。
・コスト競争力:日産
設備・人的生産性の向上のための台数増を課題としている。特に欧州、アジア、その他の地域(日米以外)が重要。台数を稼ぐとなると、B/C セグメントなど世界的にパイの大きい市場が標的になり、そこでは価格重視となる。
・グローバル供給力:トヨタ
海外での「仕組み」(系列システム)の展開・進化を課題としている。
<開発品のステージ>
・コンセプト段階:トヨタ
将来性・革新性のあるものなら短期の売上に貢献しない系列投資にも熱心で、選別を必要としている。製品化には系列の Tier1 を活用できる。
・試作品段階:ホンダ
系列投資の生産性はトヨタと日産の中間にあり、売上貢献までの時間軸も中間的だと考えられる。状況に応じて製品化には系列の Tier1 を活用できる。
・量産品段階:日産
系列投資にも短期の売上貢献が期待される。系列投資が殆どないので、製品化は自ら進めていかなければならない。
※上記の裏返しで、次のことも言えそうである。
<開発品の加工段階>
・素材レベル:トヨタ
・中間製品レベル:ホンダ
・最終製品レベル:日産
<納入までの時間軸>
・長期で構わないもの:トヨタ
・中期を考えるもの:ホンダ
・短期を期待するもの:日産
<自社の設備投資能力>
・大きい:トヨタ
グローバルでの「仕組み」ヨコテンが求められる。
・中くらい:ホンダ
系列投資への設備投資期待度は高いものの、ホンダ自身の設備投資がトヨタほどに広範囲かつ巨大ではない
・小さい:日産
日産自身が設備投資を実質的に減らしている。日産の設備を使って生産できれば同社の生産性向上にも繋がり、一層望ましいと思われる。
<開発品が対応する地域ニーズ> 各社の重点地域
・日本:ホンダ
・欧州:三社とも。特にホンダ、日産。
・アジア他:日産
以上、各社の中間決算から読み取れる仮説を述べてきた。三社の方からのここが実態と違うとか、こうした方がいいというご指摘や、新規参入をご検討中の方からの個別のご相談をお待ちしている
<加藤 真一>