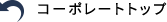自動車業界ライブラリ > コラム > 大型トレーラーが玉突き事故1人死亡。13人負傷。神奈川県…
大型トレーラーが玉突き事故1人死亡。13人負傷。神奈川県…
◆大型トレーラーが玉突き事故 1 人死亡。13 人負傷。神奈川県伊勢原市の国道で信号待ちのワゴン車など 5台に、大型トレーラーが追突。1歳9カ月の男児が死亡
◆信号待ちの軽乗用車に大型トレーラーが追突。会社員男性 (27) が重体。三重
◆熊本市の県道 (通称電車通り) で、路線バス 3台による玉突き事故。けが人なし
<2004年 7月 20日号掲載記事>
——————————————————————————–
連日のように自社製品の欠陥やトラブルが報道される中、三菱ふそうの役職員の方々のご苦労は想像に絶するものがあると思われ、現時点での最大の課題は失った信頼の回復であり、そのために品質改善に最大の努力を傾注されているものと想像される。
本誌 Vol.21 (https://www.sc-abeam.com/library/kato/kato0021-1.html)にて、「品質はブランドメッセージのカプセルでしかない」、「伝えるべきメッセージのコンテンツは別に用意されなければならない」と述べた。(これに関しては、「品質はメッセージそのものになりうるのではないか」等色々なご意見を頂いているが、後日場をあらためて回答したい。)
この考え方に立てば、三菱ふそうにとって品質の基準と管理プロセスの再設計と、全社的展開は勿論マストではあるが、必要条件であって十分条件ではないと思われる。ブランドメッセージのカプセルの再構築とともに、そのカプセルの中にどんなメッセージ、コンテンツを詰めるのかを真剣に検討する必要があろう。三菱ふそうというコーポレートブランドやその商品ブランドを、消費者や社会、その他のステークホルダーにとって、どのような意味、価値の代名詞にするかを定義すべきだということである。
筆者は、そのコンテンツとして「世界最高の安全」を提案したい。今の三菱ふそうが「世界最高の安全」を主張しても皮肉めいていて、にわかには信用を得られないと思う。だが、いずれにしても同社は安全に関する信用を競合他社並みに回復しない限り危機前の土俵には立てない。同じ努力するのであれば、競合他社並みにとどめず、一気に世界最高水準を狙うべきだと考える。
理由は3つある。
1.いくつもストレッチゴールを設けると、エネルギーやリソースが分散されてされてしまう。苦境脱出と同じ方向にある、一つの目標を立て、その達成のために全社が一つの塊になる必要がある。
2.目標を達成するのは人(社員)であり、それを助けてくれるのも人(顧客や社会)である。従って、目標は人の心を動かすものでなければならず、達成後に人が誇れる何か(三菱ふそうで働くこと、三菱ふそうの商品を買ったり、乗ったりすることが誇りになること)でなければばらない。今回の危機で、三菱ふそうは利己的な企業というイメージを持たれてしまっているから、利己的な目標(例えば売上高やシェア)では、人に誇ることが出来ない。社会的に意義のある何かでなければならない。
3.三菱ふそうの内部にその目標達成を可能にするシーズがもともとあり、市場のニーズもある。競合他社を見ても決して出遅れではなく、今からでも十分競争優位に立てる環境がある。
上記の 3 について補足したい。
まず、ここで筆者が言う「安全」とは、乗員保護のためだけの安全ではない。歩行者保護も含めた概念である。また、パッシブセーフティーだけでなく、アクティブセーフティーも含めた概念である。そうでなければ、「社会的意義のある何か」にはなりえないし、「世界最高」にもなりえない。
初めに、交通事故の現状を見ておきたい。
一般には交通事故件数は保有台数の増加に伴って増加しているが、死者数は昭和 45年をピークとして減少傾向にあり、昨年はピーク時の半分以下の 8 千人未満を達成したとされ、交通安全に関する法規制、意識やマナーのみならず、安全装備の充実の成果が上がっていると言われる。それは交通事故全体を見た場合の話である。
国土交通省が発表している「自動車運送事業用自動車事故統計年鑑」によれば、事業用自動車の圧倒的大多数を占めるトラックによる重大事故件数は昭和61年から平成 12年までの 15年間で 11% 減少したのみ、負傷者数は 13% 減、死者数は逆に 3% 増加している。
また、財団法人交通事故総合分析センターの調べでは、事業用自動車の保有台数は平成 13年で 146 万台と全体の 1.9% に過ぎないのに、第一当事者(加害者)になった事故件数は 67,128 件と全交通事故件数の 7.1%、それによる死者数は 全交通事故死者数の 9.1% と、相対的に事故の頻度と被害度が高い。
しかも、同年に事業用自動車が第一当事者(加害者)になった事故で、運転者自身はほぼ全件(96.1 %)で「無傷」であったのに対して、第二当事者(被害者。運転者または歩行者)が「無傷」であったケースは 11.0% しかない。「死亡事故」のうち、第一当事者の運転者が死亡したケースは全体の 17.6% に過ぎないのに対して、第二当事者が死亡したケースは 69.3% に達する。
(警察庁の平成 15年度の資料によると、そもそも全交通事故死者のうち、ほぼ被害者と考えてよい歩行者、自転車の死者数は各々 30.3%、自転車 12.7% の合わせて 43.0% で、加害者・被害者を含む自動車乗車中の死者数 39.4% を上回っている。)
事業用自動車による事故の態様を見ると、最大は「追突」(36.0%)で、「出会い頭衝突」(16.7%)、「横断中の歩行者との車対人」(5.5%)がこれに次ぐ。
死亡事故に限ってみると、最大は「横断中の歩行者との車対人」(21.5%)、ついで「追突」(19.8%)、「出会い頭衝突」(11.6%)。「車対人」の態様は、事故件数の 9.6% に過ぎないのに、死亡事故に限っていえば全体の 30.7% に達する。
事故発生状況を見ると、発生場所は「交差点」(55.7%)、道路線形としては「平坦な直線路」(87.7%)、天候的には「晴れ」(64.4%)、路面状態は「乾燥路」(81.5%)、運転状況は「等速直進時」(41.1%)、曜日は週末以外満遍なく、時間帯的にも車輌稼動状況に応じてほぼ満遍なく発生している(最大は午前 10時~昼 12時までの 2時間)が、死亡事故に限っていうと、午前 4時~午前 6時までの 2時間が最大である。
事故の原因(法令違反項目)としては、平成 14年度国土交通省自動車交通局自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会の調査によると、「発見の遅れ」、「判断の誤り」、「操作上の誤り」等の「人的要因」によると特定されたものが最大(46.2%)で、「整備不良」等の「車両的要因」(4.1%)や「走行環境的要因」(12.2%)が特定されたものを大きく上回っている。
長々となったが、これらの事実から言えることは、次のことである。
(1)事業用自動車の交通事故は決して特殊な状況や物理的要因で起きているのではなく、運転者の不注意や注意散漫で発生していること。
(慢性的過労など事業者のマネジメントの問題がその背景にあろう。)
(2)事業用自動車の交通事故の頻度と被害度は相対的に非常に高いこと。
(乗用車に比べて走行距離が長いことが他頻度の背景にあろう。)
(3)被害度の高い事故について、被害者は誰か(※)、発生場所や時間帯、態様はどうか等の状況がほぼ特定されていること。
※主な被害者は、運転者ではなく、他の自動車の乗員や歩行者である。
従って、自動車メーカーとしては、運転者の注意力覚醒を支援し、場合によっては車をコントロールすることで、特に交差点付近における追突の防止と、歩行者の発見や回避、不幸にして事故が発生した場合の衝撃・被害を吸収・緩和して、運転者のみならず歩行者と追突相手の乗員を保護する自動車の開発と普及が求められていることになる。
交通事故の主な原因が車両的要因にあるわけではなく、多くは事業者と運転者自身の問題であるから、自動車メーカーに責任はないという理屈は法的には間違っていないだろう。しかし、これだけの頻度と被害度での事故が発生しており、その状況が特定出来ているときに、自動車メーカーが金融業界でいうところの貸し手責任を免責されることにはならないし、少なくとも技術的に可能な範囲で何らかの対応を打つことが社会的に求められていると言えるだろう。
そのことは自動車業界も、道路交通行政もよく認識しており、自工会では1990年に「先端技術導入による事故の起きにくい自動車の研究開発」を開始し、翌年には旧運輸省の「先進安全自動車 (ASV)」の研究開発プロジェクトに発展した。従来の安全対策に加えて、最新のエレクトロニクス技術を活用した予防安全、事故回避、衝突時の被害軽減、衝突後の災害拡大の防止の 4 つの機能を盛り込んだハイテク型、インテリジェント型セーフティーカーの研究開発プロジェクトである。所管官庁の他、乗用車メーカー 9 社、財団法人日本自動車研究所、学識経験者が加わった。
1997年には、二輪車・大型車も含めた実用化の研究開発ステージである第二期(ASV-2)に移行し、2001年からは普及促進を目指した第三期(ASV-3)に突入している。
これと並行して、国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構がつくばの財団法人日本自動車研究所 (JARI) の施設を使って行なっている自動車アセスメント (JNCAP) に昨年新しい試験が追加された。欧州のユーロ NCAP では既に導入されていた「歩行者頭部保護性能テスト」である。
人間の頭部を模したインパクタを射出速度時速 35km (自動車に置き換えると時速 44km 相当で、欧州の基準の 1 割増。車対人の事故の 9 割をカバーする。)で、ボンネットからフロントガラスまでの 15分割した各エリアに向けて叩きつけ、エリアごとにインパクタが受けた衝撃を傷害値 (HIC) で表示した上で、総合得点をレベル 1~ 5 までの 5 段階評価するものである。レベル 5 では頭部に重大な傷害を受ける危険性が 10% 以下の確率になり、レベルが 1 つ下がる度に危険度が 10% ずつ上昇して、レベル 1 では 40% 以上となる。
2005年 9月以降に発売される新型車には衝撃吸収性能基準を満たすボンネットの装着が義務付けられ、2010年 9月には継続生産車にも適用となる。
代表的な ASV 技術としてどのようなものがあるか、ホンダの ASV-2 が搭載している技術で見てみたい。車線維持制御・車線逸脱警報、渋滞追従制御付きアダプティブ・クルーズコントロール、追突速度軽減システム、二輪車・四輪車相互情報通信システム(出会い頭の衝突事故防止用)、ナイト・ビジョンシステム(夜間の見えにくい歩行者を検地して画像処理して赤外線映像でヘッドアップディスプレイに表示と警告)、アクティブ・ヘッドライト等。 歩行者頭部保護性能技術としては、ワイパーピボットの変形構造化、ボンネットフード・フェンダー・バンパーの形状・素材・構造変更、インナーパネルへのショックコーン設置、ボンネットヒンジ折れ構造などがあげられる。
いずれの分野でも取組みが最も先進的で本格的なのはホンダであろう。ASV の面でも最も広範な技術を開発しており、追突速度軽減ブレーキシステムは昨年 6月に発表されたインスパイアに搭載済みである。歩行者頭部保護性能に関しても、1998年には世界初の歩行者ダミー POLAR-1 (その後 POLAR-2 に進化)を開発し、それを使って開発した「歩行者傷害軽減ボディ」を 1998年 9月発表の HR-V に装備した。そうした実績の積み重ねで、今年 6月には欧州で Jazz (日本名フィット)がユーロ NCAP の総合安全最高評価を受賞し、7月には国内でオデッセイが歩行者頭部保護基準取得第 1 号となっている。
そこで、三菱ふそうである。同社にシーズがあると述べた。
ASV プロジェクトが大型車に展開されたのは、上記の通り 1997年の ASV-2 からだが、当時乗用車と大型車の両方のフルラインメーカーであった三菱自動車は 1991年の ASV-1 の当時からプロジェクトに参加しており、大型車への展開が大型専業メーカーに比べて早かった。
実際のところ、多くの大型メーカーの取組みで製品化できているのは、ABS やエアバッグ、高剛性キャブ、衝撃吸収ステアリングホイール等、昔からあったものか、乗員保護機能どまりのものが多い。歩行者保護、他車衝撃緩和という意味では潜り込み防止用のバンパーのほか、いくつかパッシブセーフティーに関する技術くらいが実用化範囲のようだ。 予防安全、事故回避など、歩行者や他者保護のアクティブセーフティーに関するものや、パッシブセーフティーでも構造的なものは多くが研究開発段階にとどまる。
これに対して、三菱ふそうは 2000年 9月には 10 項目の実用化済み技術を含む ASV-2 を発表しているが、そのうち居眠り防止警報装置「MDAS-2」は既に市販済みであり、取組みは先行している。この装置は、フロントのカメラから蛇行を検知し、レーザーで前走車との車間を測定した上で、ハンドル操作回数などから運転者の疲労を判断する。疲労を判断すると、音声で休憩を促し、エアコンのダクトから柑橘系の匂いを送って覚醒を促す仕組みである。
この製品やその他の技術も含めて、もののよしあしは別にしても、少なくとも取組みとして遅れはとっていない。十分にこの分野でリードできる経験と知識の蓄積があるはずだ。
残念なのは、MDAS-2 はオプション設定で価格も 45 万円と高い。結果として発売から 3年間で 17台しか売れていないという(2003年 7月 23日毎日新聞)。
2002年時点での「自工会車両装備の実施状況」でも、同装置の普及率は 1.1%だ。これでは「世界最高の安全」を実現するメーカーの真剣な取組みとはいえないだろう。物流の利便性と効率を犠牲にすることなく、日本と世界からバス・トラックによる不幸な交通事故を撲滅するために三菱ふそうはある、そのために役職員一丸となって情熱と誇りを持ってそうしたクルマ作りと普及に努めるというくらいのビジョンとミッションを掲げ、それによって信用回復と再起を実現して欲しい。
大型車に関してだけ述べてきたが、三菱自工の乗用車についても同様の思いを持っている。歩行者頭部保護性能試験の結果は、コルトもグランディスもレベル 2 である。他社もレベル 3 が最高という低レベルな比較ではあるが、だからこそ抜きん出ることが可能であり、必要なのではないか。
<加藤 真一>