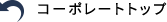自動車業界ライブラリ > コラム > 自動車部品工業、コスト圧縮に向け、部品の内製化を推進へ…
自動車部品工業、コスト圧縮に向け、部品の内製化を推進へ…
◆自動車部品工業、コスト圧縮に向け、部品の内製化を推進へ
外部委託していた部品加工の内製化を進め、変動費を年 1~ 2 億円圧縮
<2004年09月01日号掲載記事>
——————————————————————————–
外注か内作か。昔からあるテーマが今また問い直されている。
自動車産業に限らず日本の製造業の過去 10年のベクトルはほぼ一律に外注方向に向かっていた。それがここに来て多様性を増しているのだ。
流行語としては死語に近いが、バブル崩壊以来の日本企業のキーワードは、「選択と集中」であった。それは主に以下の二つの課題を意味していた。
(1)経営資源の分散を避けて、コア事業に集中投入して競争力と収益性を向上すること、
(2)固定費を削減して損益分岐点売上高を下げ、受注減への耐性を高めること。
上記二つの課題を実現していく上で、アウトソーシングには経済合理性があった。
長期的に減価償却・金利支払負担の高い設備・不動産や高賃金労働の投入が必要となる割には、稼働率、生産性、付加価値率、競争力の低い事業、プロセス、製品、サービスがどんな企業にもある。
それらを内部に抱え込み続けておくよりも、一度それらを切り出しまたは外出しし、必要なときに必要なものを必要なだけ外部から調達してきた方がコスト競争力が高く、経営資源の有効活用や損益分岐点の引き下げにも有効だ、というのがアウトソーシングの前提になる考え方である。
この考え方のもとに、日本の自動車産業でも、これまではノンコア・アセットのスピン・オフと、外部資源の活用(アウトソース)がトレンドであり、経営の定石ともなりつつあった。
ところが、ここに来て一部の企業に反対の動き、つまり内製化方向のベクトルが見られるようになってきた。これは一体どういうことだろうか。考えられることは、以下の 3 つの環境変化であろう。
1.コスト競争力の焦点の変化
2.経済合理性の変化
3.経済合理性以外の要因への関心増大
1.コスト競争力の焦点の変化
コスト競争力に関する視点が固定費から変動費にシフトしつつある。その原因として、企業のコスト体質転換(特に固定費)が進むとともに、業績回復・デフレ経済の脱却に伴い、企業の関心が受注減への体制強化(損益分岐点の引き下げ)から増産増収時の収益力向上に向かいつつあることが指摘できる。
例えば、A 社の元のコスト質が固定費 300 億円、変動費率 40% (限界利益率 60%) であったと想定してみる。
A 社の損益分岐点売上高は 500 億円である。A 社の売上高は 700 億円だが、今後の減収は避けられないと見て、コスト体質の転換を図った。固定費を 240 億円まで引き下げ、同時に固定費の変動費化を行ない、その結果変動比率は 50% (限界利益率 50%)に高まったとする。この場合、新コスト体質では損益分岐点売上高を 480 億円まで下げることができ、減収に対する耐性は高まっている。
しかし、環境が変わり、売上が減少局面にない場合はどうか。
現状の売上高 700 億円における利益は旧コスト体質では 120 億円、新コスト体質では 110 億円と微妙に減益になる。
さらに売上 1000 億円になる局面を想定すると、旧コスト体質のままであれば、300 億円の利益を上げることが出来たが、新コスト体質では 260億円の利益しか上げることができない。
これはどういうことかというと、減収局面ではコスト競争力の焦点が固定費にあった(固定費の削減と変動費化)が、固定費の体質転換がある程度進んでくると、増収局面において再び変動費のコスト競争力が焦点になってくるということを示唆している。
2.経済合理性の変化
内作よりも外注の方がコスト競争力が高いというのはどのような場合であろうか。外注先の方が設備も人も柔軟性が高く、コストが安いという場合である。
しかし、上記 1.で見たとおり、固定費体質転換(固定費の削減と変動費化)の進んだ企業においては自社の方が外注先よりも柔軟性もコスト競争力も高まっている可能性がある。
固定費削減の過程で、企業は人と設備のリストラを行なうだけでなく、多能工化と汎用設備化(フレキシブル化)を進めてきたはずである。 また、固定費の変動費化の過程で、給与体系を生活給、年齢給から成果給、業績給主体に変更し、正社員をパート、アルバイトや請負、派遣に順次置き換えてきたはずである。
その結果、固定費改革を進めた企業では、設備と人の柔軟性、コスト競争力とも、外注先とほぼ同じような構造に転換している可能性がある。パート代等は外注でも内作でも大差ないはずだ。
さらに忘れてはいけないのが物流費である。安い労賃を求めて外注先が遠距離に位置する場合は無視できないコストであり、物流費込みで内外作を比較してみると内作の方が有利ということもあろう。
特に原材料が支給品になっている場合は、往復の物流費分が確実に外注のマイナス要因になる。
冒頭「アウトソーシングには経済合理性があった」としたのは、固定費改革が進む前の段階を指してのものであり、ある程度固定費改革が進んだ今日の一部企業では必ずしも外注に経済合理性があるとは言えなくなっていると思われる。
3.経済合理性以外の要因への関心増大
コスト競争力の焦点が変化し、経済合理性自体も微妙になっていることが、外注から内作への流れの根底にあると思われるが、それ以外にも次のようなことが背景として考えられる。
(1)品質管理、生産技術の一元化、見える化
リコールや PL 問題が注目を集め、サプライヤーのリスク・テーキングや責任負担が求められ始めた中で、管理が一元化できず、できたとしても外注先現場での運用を手元で可視化できないことが外注の制約条件になってくる。
また、自社の生産管理を徹底し、ムリ・ムダ・ムラを排除しても外注先に在庫が溜まっていては完全とはいえない。
(2)短納期化対応
国際的なコスト競争が激しくなる中で日本のサプライヤーが付加価値を発揮する領域として地の利を活かした短納期対応能力は欠かせない。そこで支給品の往復だけで数日を要する外注のあり方にはメスが入る可能性がある。
(3)効率改善の意欲
ムダを減らす、品質を少しでもよくする、少しでも安く作る等、生産技術の一層の革新に向けての意欲や動機付けは、その成果が見返りを生むものでない限り、その取り組みやプロセスが評価される内部に比べて、外注先では弱くなりがちである。
以上述べてきたようなことから、外注から内作へという潮流が生まれつつある。しかし、それはまだ固定費を中心とするコスト体質転換の進んだ企業にだけ部分的に見られる傾向であるのに加えて、経営資源のコア事業への選別的集中投入という戦略自体の有効性は変わらず、外注の有効性が否定されるものではない。
各社の戦略や事業ステージ(拡大局面か縮小局面か)、体質転換の進捗度、外注先の能力や立地等から各社ごと個別に、しかし全体最適の視点で総合的に判断していく必要があろう。
<加藤 真一>