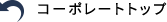自動車業界ライブラリ > コラム > 将来の中古車価格を正確に予測するシステム、プロトコーポ…
将来の中古車価格を正確に予測するシステム、プロトコーポ…
◆将来の中古車価格を正確に予測するシステム、プロトコーポなどが特許取得
中古車情報誌「GOO」を出版するプロトコーポレーションと東京海上火災保険は共同で、従来の減価償却による方法ではなく、中古車の取引データを基に、将来の中古車価格を正確に予測するシステムなどに関する特許を取得したと発表した。自動車リース契約でリース終了後の売却価格などの参考に
<2004年9月30日号掲載記事>
——————————————————————————–
中古車を取り扱う業者は勿論、リースや残価設定型ローンを扱い、時にローン滞納客からの没収・処分という形で中古車に関わる金融事業者、下取りやフリート(レンタカー会社などの大口客)からのバイバックという形で中古車に接することになる自動車メーカーや新車ディーラーにとっても、中古車の残存価格は経営上の頭痛の種だった。
新車であれ中古車であれ、いま手元にある商品の時価は分かるが、将来それがいくらになるのか見当も付かない状況とは、即ち、それを持ち続けるべきなのか、処分すべきなのか、いつどこで処分するのが得策なのか、従って現時点で取るべきアクションは何なのか、という経営の判断に必要な基礎情報も対応策も存在しないということを意味する。占い師的経営や勘と度胸の経営を余儀なくされるからである。
残価に関する失敗事例としては、北米での個人リースの失敗の結果、経営危機に陥った 90年代後半の日産を思い出す人も多いと思う。
しかし、正確には日産のケースは残価の読み誤りではない。自社の標準的残価を承知の上で政策的に高く残価を設定したもので、読み誤ったのはそれが招く結果の方である。
当時筆者も北米にいて、自動車メーカーのリース商品の設計・管理を行なっていたからよく承知しているが、北米には既に Automotive Lease Guide (ALG)という 1年経過ごとの残価指標がデファクト・スタンダードとして存在していた。全ての自動車業界関係車がこれを標準値として、残価上乗せを含むマーケティング政策的なリース商品設計を行なっていたのである。
残価を高く設定すれば、それだけユーザー側の月々の支払が安くなるから車は売りやすくなる(在庫がはける)。満期になると、ユーザーは設定残価での買取か、設定残価を元本とする再リースか、単純なメーカーへの返却かを選択できるが、設定残価がその時点での相場価格より高い場合、ユーザーが買取や再リースを選ぶ確率は減少する。どんなにその車を気に入っていたとしても、一旦返却した上で同程度の中古車を相場価格で買ってきた方が得策だからだ。 返却された車は、自動車メーカーがオークションなどを通じて処分すること
になり、相場価格=ALG の標準残価どおりだったとしても、標準値に政策的に残価上乗せした分が自動車メーカーの損失として実現する。
当然の経済原理であり、日産が承知していなかったはずはないが、あそこまで高い比率で、集中豪雨的に返却されること、また、その結果として相場価格が ALG 標準値以下に低下することを、リースを積極化させた当時の経営陣が予期していなかったか、予期していたがそれを上回る効果を見込んでいたかのどちらかである。いずれにしても、結果としては返却台数と台あたりの損失の両面から損失が膨張してしまった(こうしたリスクをヘッジするために当時北米には既に残価保険という商品があったが料率が高いため利用されていなかったのかもしれない)わけだが、これは、残価の標準という情報の欠如による結果ではない。情報を踏まえた経営判断の結果である。
日本の場合は事情が異なる。情報がなかったのだ。そのことが頭痛の種だったのである。今回、東京海上とプロトが開発した(実は開発は終わっていたが今回特許が取れた)残価予測システムは、自動車業界にとって二つの意味で朗報をもたらしたのではないか。
第一に、今回の残価予測を可能にしたロジックの応用によって自動車業界の業務プロセスの見直しが進む可能性がある。
今回、東京海上とプロトが開発したシステムの味噌は、一台一台の車が持つ属性情報を思い切ってバッサリ切り捨てたことにあると思われる。
プロトはニュース・リリースに次のように述べている。「対象財物の取引データに内在する多岐にわたる属性によりデータが細分化されることで起こるデータの減少をなくし、その残価を精度よく予測するための技術」であると。 自動車には重複する情報が沢山盛り込まれており、それらが矛盾なく整理された形になっていないために統計的に同質化や分析が可能な数のサンプルの塊だったはずが、実は統計的に使えない個別サンプルや矛盾するデータの集合になってしまうことがある。
例えば、ナンバー・プレートのうち登録陸運支局名部分は、塩の被害を受けやすい雪国や海岸沿いの出身かどうかという点で多少意味があっても、その他の数字や文字には全く意味がなく、逆にデータとして認識すると全て別々の属性として認識されてしまう。
型式 MCV20 といえば、トヨタ・ウィンダム・ 3.0G のことだが、一件目はそのデータを取るときに型式でデータを取り、二件目は車名を取ると、両者は別の属性と認識されてしまう。両方を取って、偶々グレード名を入れ間違うとデータ矛盾として統計からはねられてしまう。
色もそうである。一つ目のデータはカラーコード、二つ目はメーカーの付けるカラーネーム(ヨーロピアン・ブルーイッシュ・シルバー・マイカ等)を入れ、三つ目はその一部だけ(シルバー)を入れたり、読み換え(灰色)をしたりするとシステムでは全て別々に識別するか、はねられるかになる。
これらは今回のシステム以前の極端な例だが、情報はやたらと広げたり、深堀りしたりすればいいというのではなく、無駄な情報を敢えて切り落とすことで見えてくる重要な情報が自動車にはかなりあるということである。
業界の玄人になればなるほど次のようなことをいいがちである。
中古車は年式、走行距離、色、グレード、装備・仕様、歪み・へこみ・傷み・よれ具合、へたり・弱り具合、シミ・匂い・音、ドライバー属性など一台一台状態が異なり、どれとして同じ商品はない、だから一生掛かっても二度と同じ仕事はない、個車の属性ごとに仕事のやり方は異なるのだ、と。
現地現物の現品管理のことを言っているのであれば正しいが、全ての業務、全ての階層にこれを求めているのであれば個人企業や生業的経営から脱することはできない。商品でも顧客でも業務プロセスでも、厳密に言えば当然千差万別の中から本質的な意味や価値の違いを生むものだけに情報を削ぎ落とし、それを基準とした同質化や細分化を行なうことが経営レベルでは重要である。
さもないと、企業としての生産性や効率が達成できないことはもちろん、顧客対応のスピードの遅れや過剰なケア、それらの上乗せによる価格競争力の低下により、結果として顧客満足の低下を招く恐れがある。
第ニに、中古車市場に先物取引が生まれ、それを契機に金融工学を使ったデリバティブ商品が開発・導入されて、中古車市場の活性化や参加者拡大、中古車価格の透明化、公正化に寄与する可能性がある。
中古車市場の中心にオート・オークションがあることは、株式や外国為替等と同様である。しかし、それらは勿論のこと、ニッケルやアルミニウムやゴム等の工業製品、じゃがいもや砂糖やコーヒー豆、冷凍えび等の農水産物にも先物取引があるのに中古車市場にはそれが存在していない。
先物取引はデリバティブの入門編であり、そこからオプション取引やスワップ取引、さらにはデリバティブのデリバティブである指数取引等に発展していくが、直物しかない中古車市場は現物のまま30年間進化していない。
中古車市場に先物取引が存在しない理由として、一物一価で、放置しておくとどんどん商品価値が下がる生鮮食品特性が指摘されることがあるが、これは間違いである。商品先物相場にはブロイラーという最後には腐敗してしまう本当の生鮮食品が上場されている。中古車と同様、実は鳥種も重量も肉付き・羽根付きも鮮度も匂いも異物の付着や外傷の度合いも一つ一つ異なるのを検査と格付けによって標準化して立派に上場を果たしている。
中古車市場に先物取引が導入されないもう一つの理由として、業界が小さく、実需取引の拡がりや推定出来高が小さいためにボラティリティーが大きく、公正な価格形成やヘッジ機能が発揮できないことが指摘される。
しかし、オート・オークションで年間 6 百万台(出品台数だが、成約も約 4 百万台)の取引があるのに対して、東京工業品取引所(国内商品先物の半分以上を独占し、世界第 13 位の商品先物取引所)における銀、パラジウム、アルミニウム、原油の出来高は年間 100 万枚(取引件数のこと)かそれ以下の取引しかない。年間出来高 25 百万枚と今や金を上回って商品先物の主役になったガソリンですら 99年の同取引所上場当時の出来高は 4 百万枚未満に過ぎなかった。
商品先物の上場基準には、上記の品質の均一性や十分な流通量、少数の当事者に支配されない商品特性の他に、国際性や情報の開示が挙げられる。日本の中古車は年間 100 万台が輸出されている国際商品である。となると、中古車の先物取引が始まらない最大の問題は情報の不足、非対称性にあったということができる。今回の残価予測システムは、市場の裁定を経たものではないので完璧なものかどうかは別にして、残価に関するシグナルを発することで先物取引の発生やその先にある各種の金融商品の派生、リスクヘッジ機能の発揮、実需以外の市場参加者の獲得や、国際的に見て不当に低い水準にある中古車価格の適正化に貢献することが期待される。
<加藤 真一>